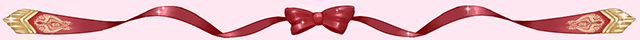
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
永遠の恋〜信長の寵妃【イケメン戦国】
第110章 魔王の霍乱
翌日、朱里は家康とともに薬草を集めるために城外にある山の麓へと来ていた。
「家康、これはどうかな?使えそう?」
「うん。それは葉だけじゃなくて根も使えるから、根も傷付けないように引き抜いて」
「分かった。気を付けるね」
葉元の部分を掴み、土の下の根が千切れてしまわないように慎重に引き抜いて、根に付着した泥を軽く落としてから籠の中へとそっと入れた。
「やっぱりこの時期は自生している薬草も少ないね」
枯れ葉が散らばった地面を踏み分けつつ周囲を見回して解熱に使える薬草を探すが、やはり季節柄か豊富に生えているとは言い難かった。それでも少しでも多くの薬草を採取して帰らなければと、地面に目を凝らす。
「冬場だから仕方ないけど、これからは急な入用に備えて予め多めに備蓄しておくことも考えないといけないな。豊富に集められる時に集めて乾燥させておけば、いつでも使えるしね。病の流行はいつ起こるとも知れないから…備えておくに越したことはないよ」
「そうだね。薬がもっと誰でも気軽に手に入れられるようになれば、病に罹っても助かる命が増えるかもしれないよね。信長様もきっとそうお考えだと思うの」
戦や飢え、病によって人々の命があまりにも容易く失われるこの時代にあって、政を行う者の責任はこの上なく重い。
相次ぐ戦や一揆の制圧を経て天下布武を為し遂げた信長を人の命を軽んじる非道の者だと悪しく罵る者も少なくないが、真実は決してそうではない。数多の命を犠牲にせざるを得なかったからこそ、人の命の重さを誰よりも深く感じているのは信長自身だったのだ。
時に非情な決断をしながらも己の信じる大義を掲げて乱世を駆け抜けてきた信長だが、その道行きのなかで力無き弱き者達を見捨てることはなかった。それは己の家臣や自国の民百姓に限らず、敵も味方も全てにおいてである。
『力のある強き者は力の無い弱き者を守る責務がある』
身内同士で互いに争い合い、初めて人を殺めた幼き頃。
力を手に入れ強くなり乱世を終わらせるのだと己自身に誓ったあの日から、信長の心の奥底にあるのは弱き者への慈しみの心なのだった。
「家康、これはどうかな?使えそう?」
「うん。それは葉だけじゃなくて根も使えるから、根も傷付けないように引き抜いて」
「分かった。気を付けるね」
葉元の部分を掴み、土の下の根が千切れてしまわないように慎重に引き抜いて、根に付着した泥を軽く落としてから籠の中へとそっと入れた。
「やっぱりこの時期は自生している薬草も少ないね」
枯れ葉が散らばった地面を踏み分けつつ周囲を見回して解熱に使える薬草を探すが、やはり季節柄か豊富に生えているとは言い難かった。それでも少しでも多くの薬草を採取して帰らなければと、地面に目を凝らす。
「冬場だから仕方ないけど、これからは急な入用に備えて予め多めに備蓄しておくことも考えないといけないな。豊富に集められる時に集めて乾燥させておけば、いつでも使えるしね。病の流行はいつ起こるとも知れないから…備えておくに越したことはないよ」
「そうだね。薬がもっと誰でも気軽に手に入れられるようになれば、病に罹っても助かる命が増えるかもしれないよね。信長様もきっとそうお考えだと思うの」
戦や飢え、病によって人々の命があまりにも容易く失われるこの時代にあって、政を行う者の責任はこの上なく重い。
相次ぐ戦や一揆の制圧を経て天下布武を為し遂げた信長を人の命を軽んじる非道の者だと悪しく罵る者も少なくないが、真実は決してそうではない。数多の命を犠牲にせざるを得なかったからこそ、人の命の重さを誰よりも深く感じているのは信長自身だったのだ。
時に非情な決断をしながらも己の信じる大義を掲げて乱世を駆け抜けてきた信長だが、その道行きのなかで力無き弱き者達を見捨てることはなかった。それは己の家臣や自国の民百姓に限らず、敵も味方も全てにおいてである。
『力のある強き者は力の無い弱き者を守る責務がある』
身内同士で互いに争い合い、初めて人を殺めた幼き頃。
力を手に入れ強くなり乱世を終わらせるのだと己自身に誓ったあの日から、信長の心の奥底にあるのは弱き者への慈しみの心なのだった。
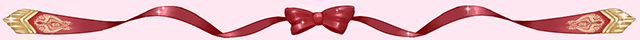
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする