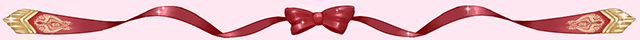
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
永遠の恋〜信長の寵妃【イケメン戦国】
第110章 魔王の霍乱
今この時も病で苦しみ命を落としている人が数多いるというのに、自分一人何もできず、城の中で守られていることが歯痒くて堪らなかった。
「お願いします、信長様っ!私にも何かやらせて下さい!」
「朱里…」
(直接現地に行って手伝えなくても、私にも何かできることはあるはず…)
「……じゃあ、あんた、俺を手伝ってくれない?」
「えっ…あ、家康?」
早々に広間を出て行こうとしていた家康だが、朱里が声を上げるのを聞いて自然と足を止めていた。
心優しく責任感の強い朱里が病に苦しむ民達のために何かしたいと思う気持ちは家康にもよく理解できたが、現場の状況が完全に把握できていないところに朱里を連れて行くことを信長が許さないだろうということも容易に想像がついた。
それでも、家康は朱里の願いを叶えてあげたいと思ったのだ。
「薬草集めと薬作り、手伝ってくれない?急なことだから人手が足りないんだ。多少なりとも薬の知識があるあんたが手伝ってくれると助かるんだけど…」
「え…あ、いいの?」
「信長様が許してくれるならね。俺と一緒に城外へ薬草を採りに行くぐらいなら危ないことはないと思いますし…俺に朱里を貸してもらえませんか?信長様」
「ふっ…天下人の妻を貸してくれとは…貴様、随分と言うようになったな、家康。まぁ、よい。朱里、貴様には家康の手伝いを命じる。が、無理はするな」
「は、はいっ!ありがとうございます、信長様!」
困ったような複雑な表情を浮かべながらも、信長は家康の進言を受け入れた。民達のために何かしたいという朱里の健気な思いは信長にもまた理解できたし、家康とともに薬草を集めるぐらいなら危険なこともなかろうと思ったからだ。
そもそも朱里が家康から薬学や医術を学び始めたのは、信長の正室として城の者や家臣達のために役に立つ知識を身に付けたいと自ら願ったからだった。
『誰かの役に立ちたい』
そんな風に思うことは朱里にとっては生まれながらに当たり前のことのようだったが、そういう心根の優しさや純粋さを信長は好ましいと思うのだった。
関東一の大国、北条家の姫としてこの世に生を受けて大切に育てられ、天下人の妻となっても、自分よりも他者を優先し、表裏なく思い遣る朱里の澄んだ心が変わることはなかったのだ。
「お願いします、信長様っ!私にも何かやらせて下さい!」
「朱里…」
(直接現地に行って手伝えなくても、私にも何かできることはあるはず…)
「……じゃあ、あんた、俺を手伝ってくれない?」
「えっ…あ、家康?」
早々に広間を出て行こうとしていた家康だが、朱里が声を上げるのを聞いて自然と足を止めていた。
心優しく責任感の強い朱里が病に苦しむ民達のために何かしたいと思う気持ちは家康にもよく理解できたが、現場の状況が完全に把握できていないところに朱里を連れて行くことを信長が許さないだろうということも容易に想像がついた。
それでも、家康は朱里の願いを叶えてあげたいと思ったのだ。
「薬草集めと薬作り、手伝ってくれない?急なことだから人手が足りないんだ。多少なりとも薬の知識があるあんたが手伝ってくれると助かるんだけど…」
「え…あ、いいの?」
「信長様が許してくれるならね。俺と一緒に城外へ薬草を採りに行くぐらいなら危ないことはないと思いますし…俺に朱里を貸してもらえませんか?信長様」
「ふっ…天下人の妻を貸してくれとは…貴様、随分と言うようになったな、家康。まぁ、よい。朱里、貴様には家康の手伝いを命じる。が、無理はするな」
「は、はいっ!ありがとうございます、信長様!」
困ったような複雑な表情を浮かべながらも、信長は家康の進言を受け入れた。民達のために何かしたいという朱里の健気な思いは信長にもまた理解できたし、家康とともに薬草を集めるぐらいなら危険なこともなかろうと思ったからだ。
そもそも朱里が家康から薬学や医術を学び始めたのは、信長の正室として城の者や家臣達のために役に立つ知識を身に付けたいと自ら願ったからだった。
『誰かの役に立ちたい』
そんな風に思うことは朱里にとっては生まれながらに当たり前のことのようだったが、そういう心根の優しさや純粋さを信長は好ましいと思うのだった。
関東一の大国、北条家の姫としてこの世に生を受けて大切に育てられ、天下人の妻となっても、自分よりも他者を優先し、表裏なく思い遣る朱里の澄んだ心が変わることはなかったのだ。
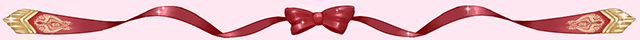
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする