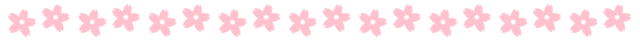
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
貴女の血を【R18】
第2章 桜降る季節
「何で泣くの。僕のこと怖いの?あのカフェでは僕のことあんなに見てたのに、もう僕のこと忘れちゃったの?」
彼はやっぱり冷たい表情で。
「忘れてないけど……」
私に言えるのはこれが精一杯。
忘れようとしてたなんて言えないし、
それを聞いた彼の表情が少し柔らかくなったように見えた。
「じゃ、あのカフェで明日の1時に待ってるから。絶対来てね」
彼はそういうと、どこかへ消え去った。
私は全身の力が抜けて、地面に座り込んだ。
何もされなかった。手首を掴まれただけでそれ以上触れない。
少し複雑な気持ちだった。
私の手首には、彼のぬくもりさえ感じない。
「明日の1時……」
期待してしまう。それに、彼のこと知りたいし…
桜咲く季節。私の中の何かが咲き始めているようだった。
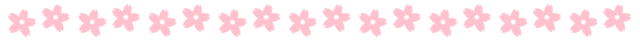
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする