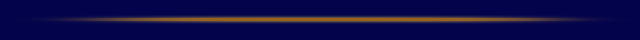
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【NARUTO】月影の恋人(R18)
第7章 門出
「大丈夫!?
喉を火傷してるみたいやから、喋ったあかんよ!
すぐお医者さん呼んでくるから!」
椅子から立ち上がり走り出そうとするとわたしをカカシが止める。
「結は傍にいてやりな。
オレが行ってくる」
「あ、ありがとう」
わたしがいい終わるより前にカカシは部屋を出て行った。
わたしはもう一度椅子に座ると、背中を見せて咽せる親父さまの背中を撫でた。
親父さまに触れたのはいつ以来だろう……。
年、取ったなぁ。
白髪の混じる頭を見ながら、大きな背中を撫で続ける。
「結、行ってこい」
「え?どこへ?」
「アイツと宿、泊まってこい」
「なん、で?」
遊女が花街を出ることは禁じられている。
規則にうるさい親父さまがそんなことを言うなんて意外だった。
「深い理由はない。
アイツも言うてたやろ。
花街はどこも混乱してる。
ひとりでも少ない方がいいやろ」
親父さまがチラリとこちらを向いて、またすぐにそっぽを向いてしまう。
「う、ん。
わかった」
「そういうことや。
結のこと頼んだで。
明日、花黎館に2人で来てくれ」
「はい」
いつの間にか先生を連れて戻ってきたカカシが相槌をうつ。
親父さまは、手で支えて体を少し起こしカカシを睨むように見すえると、しんどいのか、またすぐに布団に身を横たえてしまった。
花黎館とは、わたしがいた妓楼とほど近い店で、親父さまとそこの楼主とは旧知の仲だった。
「親父さま、無理したらアカンで」
親父さまはもう喋らず、早く出てけとでも言うように手をしっしっと振る。
心配やけど、診療所にいるんが1番安心やんな。
わたしは親父さまから視線を外し、病室の入り口にいたカカシの方に向かう。
「親父さま、明日行くからね。
ゆっくり休んでな。おやすみ」
親父さまからの返事はない。
医者嫌いだから心配で最後に振り返ると、親父さまは大人しく医者の診察を受けていた。
わたしはホッとして、カカシと診療所を後にした。
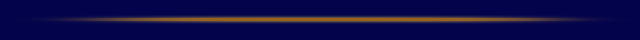
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする