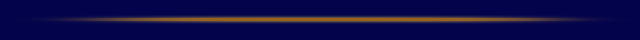
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【NARUTO】月影の恋人(R18)
第3章 奇跡の夜、口付けの朝
「ちょ、何して!?」
立ち上がり夕月の手を止めようとするが、するりとかわされてしまう。
腰紐が解かれると、夕月の白い胸元が露わになった。
「っ……」
慌てて目を逸らそうとしたとき、その綺麗な肌には似つかわしくない古い、大きな傷跡が見えた。
「それ……」
傷は心臓と肺のちょうど真ん中あたりにあった。
だが、間には何本もの太い、大事な血管が通っている。
死ななかったのは奇跡に近い。
「この傷は強盗に襲われたときにできたやつやねん。
胸にこんな大きい傷あんのに動いてるから幽霊やて。
遊女やのに致命的やろ?
なんであんとき両親と一緒に逝けへんかったんやろって、わたしだって何回も思ったわ……!!」
稚拙な悪口。
でも、この逃げ場のないせまい世界で生きる夕月にとっては、それはとても辛いことだっただろう。
夕月の悲痛な言葉は、彼女の心の傷の深さを物語っていた。
オレは襦袢の合わせをしっかり閉じ腰紐を結び直すと、悲しげに顔を歪める夕月を抱き寄せた。
「その傷で死ななかったんだから、夕月は幽霊じゃなくて強運の持ち主じゃない。
しかも、奇跡って言ってもいいくらいの。
オレは今日、夕月と一緒に酒が飲める奇跡が、すごく嬉しい……」
慰めにも何にもならないけど、オレは今の素直な気持ちを口にした。
すると夕月が、クシャリと泣きそうに顔を歪めた。
「っ、そんなん言われたん、初めてや……」
ただ棒立ちになってされるがまま抱きしめられていた夕月が、遠慮がちにオレの肩口に頬を寄せ、背中に手を回す。
その肩は少し震えていて、泣いているのかもしれなかった。
意地っ張りな夕月は、オレに涙なんて見られたくないだろう。
オレは涙を隠すように、夕月の細い肩をいっそう強く抱きしめた。
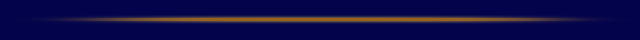
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする