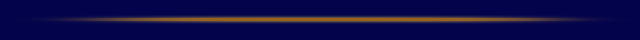
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【NARUTO】月影の恋人(R18)
第3章 奇跡の夜、口付けの朝
「そうなんや!お疲れさま!」
満面の笑顔で夕月が笑う。
「だから、せっかくだし酒が飲みたいんだけど付き合ってくれる?」
「うん!あ!じゃあ座敷行く?
姐さんらに踊ってもらう??」
大張り切りで夕月が立ち上がる。
「んーん。オレ遊郭は苦手なんだって。
だから、夕月と2人で飲みたい」
ウソは言っていない。
でも自分にまったく下心がないかと問われたら、自信もなかった。
そんなオレのよこしまな気持ちに気づきもせずに、夕月がすっくと立ち上がる。
「そっか!そうやんな!
じゃあちょっと厨房行ってお酒と適当におつまみも頼んでくるな!
おつまみリクエストある?」
「ん、じゃあ揚げだし豆腐と白子ポン酢」
前に大名に連れられて来たときに、美味しかったものだ。
「わかった!」
さっきまでの不機嫌から一転、夕月はご機嫌で出ていった。
運ばれてきたお酒とつまみで乾杯する。
キンとよく冷えた冷酒は、乾いた喉に心地よい苦味を残して流れていった。
「この酒、美味いね」
「やろ?これめっちゃ好きやねん」
夕月もいいペースで酒を飲む。
初めて会ったときも一人で飲んでいたし、お酒が好きなのだろう。
飲むと夕月は、いつもより饒舌になった。
さっきの取っ組み合いの理由も自分から話してくれた。
どうやら前にあった男に襲われた事件のせいで、夕月とオレが恋仲だと言う噂が流れていて、それに嫉妬した遊女が夕月に嫌がらせをしてきたらしい。
「なんかゴメンね。
オレのせいだったんだ」
「別にカカシのせいちゃうよ。
カカシはわたしを助けてくれただけやろ?
それに、寝屋での仕事も減ったし逆にラッキーなくらいやわ」
「え?なんで寝屋の仕事が減るの?」
「お客さんの間で火影の女に手ぇ出したら殺されるって噂が流れてるらしいで。
それに幽霊やて言われてるから、もともと他の遊女より相手すること少ないし」
男が寄ってこないのはいいけど、さっきから気になってた幽霊という言葉が引っかかる。
「さっきも思ったけど、なんで夕月が幽霊なの?」
「知りたい?」
夕月の表情が、さっきと打って変わって翳る。
聞いていいものかと思案している間に、夕月が立ち上がってこっちに来る。
そして、おもむろに羽織を脱いで帯を緩めた。
満面の笑顔で夕月が笑う。
「だから、せっかくだし酒が飲みたいんだけど付き合ってくれる?」
「うん!あ!じゃあ座敷行く?
姐さんらに踊ってもらう??」
大張り切りで夕月が立ち上がる。
「んーん。オレ遊郭は苦手なんだって。
だから、夕月と2人で飲みたい」
ウソは言っていない。
でも自分にまったく下心がないかと問われたら、自信もなかった。
そんなオレのよこしまな気持ちに気づきもせずに、夕月がすっくと立ち上がる。
「そっか!そうやんな!
じゃあちょっと厨房行ってお酒と適当におつまみも頼んでくるな!
おつまみリクエストある?」
「ん、じゃあ揚げだし豆腐と白子ポン酢」
前に大名に連れられて来たときに、美味しかったものだ。
「わかった!」
さっきまでの不機嫌から一転、夕月はご機嫌で出ていった。
運ばれてきたお酒とつまみで乾杯する。
キンとよく冷えた冷酒は、乾いた喉に心地よい苦味を残して流れていった。
「この酒、美味いね」
「やろ?これめっちゃ好きやねん」
夕月もいいペースで酒を飲む。
初めて会ったときも一人で飲んでいたし、お酒が好きなのだろう。
飲むと夕月は、いつもより饒舌になった。
さっきの取っ組み合いの理由も自分から話してくれた。
どうやら前にあった男に襲われた事件のせいで、夕月とオレが恋仲だと言う噂が流れていて、それに嫉妬した遊女が夕月に嫌がらせをしてきたらしい。
「なんかゴメンね。
オレのせいだったんだ」
「別にカカシのせいちゃうよ。
カカシはわたしを助けてくれただけやろ?
それに、寝屋での仕事も減ったし逆にラッキーなくらいやわ」
「え?なんで寝屋の仕事が減るの?」
「お客さんの間で火影の女に手ぇ出したら殺されるって噂が流れてるらしいで。
それに幽霊やて言われてるから、もともと他の遊女より相手すること少ないし」
男が寄ってこないのはいいけど、さっきから気になってた幽霊という言葉が引っかかる。
「さっきも思ったけど、なんで夕月が幽霊なの?」
「知りたい?」
夕月の表情が、さっきと打って変わって翳る。
聞いていいものかと思案している間に、夕月が立ち上がってこっちに来る。
そして、おもむろに羽織を脱いで帯を緩めた。
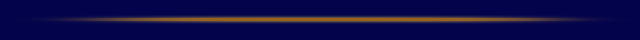
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする