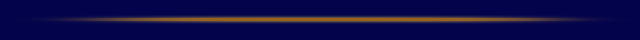
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【NARUTO】月影の恋人(R18)
第3章 奇跡の夜、口付けの朝
夕月を抱きしめて、オレより少し高い体温を感じていると、酒のせいもあり、だんだんと眠くなってくる。
「っと……」
ふらりと体を揺らしたオレに、夕月が顔を上げる。
「カカシも酔った?」
少し濡れた夕月の目元が優しげに緩められる。
「ん、そーかも」
「そろそろ寝よっか」
「うん」
布団に潜り込むと、夕月がオレの手を握る。
初めて一緒に寝た日以来なのにその手が落ち着くのは、二人の距離が少し縮まったからかもしれない。
「……今日は酔ってるから、手、繋いでいい?」
そんな言い訳、もういらないのに。
律儀に聞いてくる夕月が可愛い。
「別に酔ってなくてもいつでもいいよ」
「ほんま?」
「うん」
夕月が嬉しそうに笑って少しだけオレの方に近づく。
友達でもない、恋人でもない、微妙な距離は、今のオレたちの関係みたいだ。
「……今日の喧嘩な」
「うん」
眠る前の、いつもより少しかすれた夕月の優しい声に、微睡んでいた目をなんとか開ける。
「最初はただ言い合いやってんけど、カカシに貰った手紙破かれそうになって、手出すん我慢できんかった。
親父さまに明日ドヤされるやろなぁ」
あんな紙切れを守るために?
「馬鹿だね。
あんなメモ、どうでもいいでしょ?」
「だって、カカシから貰った、はじめての手紙やから……」
言いながら自分が言ったことが恥ずかしくなったのか、夕月の顔がみるみる赤く染まっていく。
あー、もー。
可愛い。
オレが理性保つためにどんだけ苦労してるか、この子は絶対わかってないんだろうな。
でも……。
流されて、中途半端な関係のままで、絶対抱きたくない。
嫌われてない気はするけど……。
夕月がオレのこと好きって思ってくれるように、オレももうちょっと頑張らないとね。
「夕月……」
「なに?」
「やっぱオレ、夕月のホントの名前、知りたい」
少しでも、夕月のこと知りたい。
「アカン」
「名前教えてくれたら元気でそうなのに」
「……」
口を開き何か言いかけた夕月が、すぐに口をつぐんで黙ってしまう。
眉間にはしわ。
手強いね。どうも。
でも、今日は夕月のことを少し知れたし、もう十分だ。
「まぁ、考えといて…、よ……」
オレは心地よい温もりと匂いに眠気を堪えられなくなり、ゆっくりと目を閉じた。
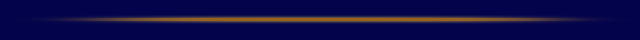
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする