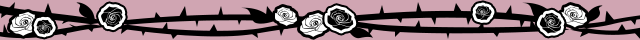
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【ONE PIECE】人はそれを中毒という
第11章 露呈
一か八かの賭けだった。
手にした彼女の電伝虫を見つめながらたっぷりと数日悩んだ。
ずっと鳴っていたのは知っていた。
本部への帰還で見張りがいる最中、静かに震えていたそれを手に取ることは出来なかったが、しつこいくらいに相手はこちらに掛けてきていた。
だから一人になれた今、勝手に使う罪悪感を持ちながらも受話器を取ろうとしては、躊躇していた。
ただでさえ私物を勝手に持ち出し、触れられたくなさそうな電伝虫の相手に連絡を取ろうとしているのだ。
だが、彼女から見限られようとも現状を打破しなければ怒りを向けられる機会もなく彼女との繋がりは切れてしまう。
力があればこんなにも悩みはしないのに、所詮彼女の庇護下にいた自分が彼女の危機を打開できる筈もなかった。
誰に見られているわけでもなく、静かな空間で息を押し殺してようやく受話器に手を掛ける。
間抜けな電伝虫のコール音がやけに響く。
何回唾を飲み込んだかわからないが、たっぷり時間を置いた後、相手が電話に出た。
『………』
やはり警戒している。
なんども連絡しても出なかったのだ、異変には気付いているのだろう相手は、今この電話口にいるのがクロエではないことに気付いている。
少なくとも頭が回る相手と確認できて安心した。
「……クロエ中将の…大切な方と繋がる電伝虫と、伺っています…」
喋らない相手に問い掛ける。
誰でも構わない。彼女を助けられそうだと判断したいから、少しだけでも声を聞かせてほしい。
「そちらが誰なのかとかは、問いませんが…クロエ中将が大事だと言っている方ならば…ひとつ、お願いが…」
何故だが相手がこちらにきちんと傾聴していると確信が持てる。
伝わる筈もない空気がそういっていた。
「力を…貸してくれませんか…彼女を、助けていただけませんかッ…」
懇願だった。
どうか、力のない自分に代わり助け出して欲しい。
彼女があんな拘束のされ方をする程、重い罪を犯しているなんて考えられない。
ぎゅっと受話器を握りしめ、祈るように返事を待つ。
どうか、応えてくれと願って。
『詳しく聞かせろ』
待ちわびた声に心臓が強く脈打つ。
短い言葉だが、その低く淀みない声に、助かってもいないのにあぁもう大丈夫だと安心感が身体を巡った。
手にした彼女の電伝虫を見つめながらたっぷりと数日悩んだ。
ずっと鳴っていたのは知っていた。
本部への帰還で見張りがいる最中、静かに震えていたそれを手に取ることは出来なかったが、しつこいくらいに相手はこちらに掛けてきていた。
だから一人になれた今、勝手に使う罪悪感を持ちながらも受話器を取ろうとしては、躊躇していた。
ただでさえ私物を勝手に持ち出し、触れられたくなさそうな電伝虫の相手に連絡を取ろうとしているのだ。
だが、彼女から見限られようとも現状を打破しなければ怒りを向けられる機会もなく彼女との繋がりは切れてしまう。
力があればこんなにも悩みはしないのに、所詮彼女の庇護下にいた自分が彼女の危機を打開できる筈もなかった。
誰に見られているわけでもなく、静かな空間で息を押し殺してようやく受話器に手を掛ける。
間抜けな電伝虫のコール音がやけに響く。
何回唾を飲み込んだかわからないが、たっぷり時間を置いた後、相手が電話に出た。
『………』
やはり警戒している。
なんども連絡しても出なかったのだ、異変には気付いているのだろう相手は、今この電話口にいるのがクロエではないことに気付いている。
少なくとも頭が回る相手と確認できて安心した。
「……クロエ中将の…大切な方と繋がる電伝虫と、伺っています…」
喋らない相手に問い掛ける。
誰でも構わない。彼女を助けられそうだと判断したいから、少しだけでも声を聞かせてほしい。
「そちらが誰なのかとかは、問いませんが…クロエ中将が大事だと言っている方ならば…ひとつ、お願いが…」
何故だが相手がこちらにきちんと傾聴していると確信が持てる。
伝わる筈もない空気がそういっていた。
「力を…貸してくれませんか…彼女を、助けていただけませんかッ…」
懇願だった。
どうか、力のない自分に代わり助け出して欲しい。
彼女があんな拘束のされ方をする程、重い罪を犯しているなんて考えられない。
ぎゅっと受話器を握りしめ、祈るように返事を待つ。
どうか、応えてくれと願って。
『詳しく聞かせろ』
待ちわびた声に心臓が強く脈打つ。
短い言葉だが、その低く淀みない声に、助かってもいないのにあぁもう大丈夫だと安心感が身体を巡った。
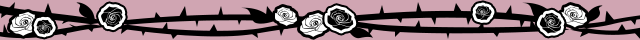
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする