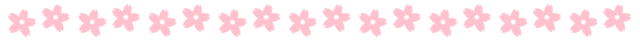
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
きみを想う
第12章 贈り物
でもその目はすぐに笑みに変わり、「仰せのままに、お姫様」と言って、コロンとわたしが下になるように体制を変えると、優しく唇を重ねた。
啄むような口づけは、だんだんと深いものになっていく。
2人の吐息が、キスの中に溶けていく。
カカシの手がわたしの体を上から順番に撫でていく。
「んっ…」
ゾワリと鳥肌がたち、声が漏れてしまう。
太ももを撫でていた手がわたしの足を軽く開かせると、カカシがその間に体を割りこませた。
「…っ、カカシ…」
離れた唇で名前を呼ぶと、愛おしそうな顔で、髪を撫でてくれる。
「すずらん、したい…」
熱を孕んだカカシの目が、吐息がわたしを誘う。
最近カカシが忙しかったり、私の生理が重なったりで、わたしたちはぜんぜん体を重ねていなかった。
昂った感情のまま、カカシの首に手を巻きつけてカカシの頭を抱き寄せる。
「わたしも、したい…」
朝からはしたないとわかっていても、我慢できない。
わたしたちは、欲望のままに愛し合った。
気怠い体をもぞ、と動かしうっすら目を開ける。
数回瞬きしてから辺りを見回すと、西の窓からオレンジの光が差し込んでいる。
ガバッ!!
慌てて身を起こす。
何も身につけていない上半身には、カカシがつけた赤い跡がたくさん残っていて、思わず顔が熱くなる。
どうやらわたしたちは何度も身体を重ねたあと、そのまま意識を手放してしまったようだ。
「か、カカシ!!」
隣で気持ちよさそうに眠るカカシの肩を揺する。
「んー…」
カカシがコロンと寝返りを打って、ボーッとした顔で目を開ける。
そして同じようにガバッと起き上がり、辺りを見回す。
「あっえ!?オレ寝ちゃったの?」
慌てているカカシが珍しくて思わず笑ってしまう。
「みたい。
わたしも今気がついたの」
「すずらんの誕生日が…」
「あはは。大丈夫だよ。
わたしはカカシがゆっくり寝れて嬉しい。」
肩を落とすカカシの頬に励ますように口づける。
そんなわたしをチラリと見て、カカシが体重をかけて横から抱きついてくる。
「ごめん。ほんっとごめん」
「カカシ!重いよ!わっ!!!」
支えきれなくて、ポフっと2人でベッドに沈み込む。
啄むような口づけは、だんだんと深いものになっていく。
2人の吐息が、キスの中に溶けていく。
カカシの手がわたしの体を上から順番に撫でていく。
「んっ…」
ゾワリと鳥肌がたち、声が漏れてしまう。
太ももを撫でていた手がわたしの足を軽く開かせると、カカシがその間に体を割りこませた。
「…っ、カカシ…」
離れた唇で名前を呼ぶと、愛おしそうな顔で、髪を撫でてくれる。
「すずらん、したい…」
熱を孕んだカカシの目が、吐息がわたしを誘う。
最近カカシが忙しかったり、私の生理が重なったりで、わたしたちはぜんぜん体を重ねていなかった。
昂った感情のまま、カカシの首に手を巻きつけてカカシの頭を抱き寄せる。
「わたしも、したい…」
朝からはしたないとわかっていても、我慢できない。
わたしたちは、欲望のままに愛し合った。
気怠い体をもぞ、と動かしうっすら目を開ける。
数回瞬きしてから辺りを見回すと、西の窓からオレンジの光が差し込んでいる。
ガバッ!!
慌てて身を起こす。
何も身につけていない上半身には、カカシがつけた赤い跡がたくさん残っていて、思わず顔が熱くなる。
どうやらわたしたちは何度も身体を重ねたあと、そのまま意識を手放してしまったようだ。
「か、カカシ!!」
隣で気持ちよさそうに眠るカカシの肩を揺する。
「んー…」
カカシがコロンと寝返りを打って、ボーッとした顔で目を開ける。
そして同じようにガバッと起き上がり、辺りを見回す。
「あっえ!?オレ寝ちゃったの?」
慌てているカカシが珍しくて思わず笑ってしまう。
「みたい。
わたしも今気がついたの」
「すずらんの誕生日が…」
「あはは。大丈夫だよ。
わたしはカカシがゆっくり寝れて嬉しい。」
肩を落とすカカシの頬に励ますように口づける。
そんなわたしをチラリと見て、カカシが体重をかけて横から抱きついてくる。
「ごめん。ほんっとごめん」
「カカシ!重いよ!わっ!!!」
支えきれなくて、ポフっと2人でベッドに沈み込む。
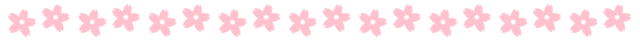
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする