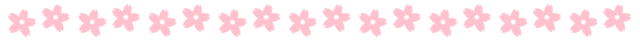
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
きみを想う
第6章 誕生日
「そーなんだ。
今度アイツらになんか奢らなきゃな」
「ふふ、そうだね」
カカシがわたしの手を取り指を絡める。
「すずらんもありがとね」
「ううん、カカシの先生姿が見れて楽しかったよ。
みんなにすごく慕われてるんだなぁって、わたしも嬉しかった」
カカシがニコリと笑って繋いでた手を持ち上げて、唇に押し当てる。
それだけでわたしの体温が上昇してしまう。
「改めて、お誕生日おめでとう」
「ありがと」
考えに考えぬいたプレゼント、やるなら今だ。
そう思い、カカシにちょっと待ってねっと言って自分の荷物のところに用意を取りに行く。
「あのね。プレゼント。
色々考えたんだけど、どうしても何がいいか思いつかなくて、それで、カカシ、ずっと仕事でなかなか休めないでしょ?
夜もわたしに会いにきてくれてるし。
だから、ちょっとでも安らいでほしくて、これを持ってきてみました」
パッと出したのは耳かきとバスタオル。
カカシが目を丸くしている。
「耳かき??」
「そ、小さい頃の朧げな記憶だけど、お母様がよくお父様にやってあげてたの。
なんでなのって聞いたら、疲れた時にしてもらうと元気になれるんだって言ってた。
だから、わたしもカカシにしてあげたくて。
しても、いいかな?」
「じゃあ、お言葉に甘えようかな」
珍しくカカシが照れていて、わたしもなんだか照れてしまう。
近くにあったソファに座ってカカシに横になってもらう。
膝にバスタオルを引こうとするとそのままがいいと言って、わたしのお腹の方に顔を向けてわたしの膝に頭を乗せる。
「……なんか照れるね。
耳そうじなんて、誰かにやってもらうの子供の時以来だよ……」
「そうだよね。
痛かったら言ってね」
「うん」
カカシの少しチクチクする銀髪を撫でて、そっと耳かきを入れる。
思った以上にドキドキするな。
「人にやってもらうのって、こんな気持ちーんだ……。
イッシン様の気持ち、わかったかも……」
「本当?よかった。
じゃあ、反対向いて貰っていい?」
するとカカシが一度立ち上がり、わたしをソファの反対の端に追いやる。
「こうした方が、すずらんにひっつけるから」
そう言ってわたしの膝にまた転がると、両手をわたしの体に巻きつける。
今度アイツらになんか奢らなきゃな」
「ふふ、そうだね」
カカシがわたしの手を取り指を絡める。
「すずらんもありがとね」
「ううん、カカシの先生姿が見れて楽しかったよ。
みんなにすごく慕われてるんだなぁって、わたしも嬉しかった」
カカシがニコリと笑って繋いでた手を持ち上げて、唇に押し当てる。
それだけでわたしの体温が上昇してしまう。
「改めて、お誕生日おめでとう」
「ありがと」
考えに考えぬいたプレゼント、やるなら今だ。
そう思い、カカシにちょっと待ってねっと言って自分の荷物のところに用意を取りに行く。
「あのね。プレゼント。
色々考えたんだけど、どうしても何がいいか思いつかなくて、それで、カカシ、ずっと仕事でなかなか休めないでしょ?
夜もわたしに会いにきてくれてるし。
だから、ちょっとでも安らいでほしくて、これを持ってきてみました」
パッと出したのは耳かきとバスタオル。
カカシが目を丸くしている。
「耳かき??」
「そ、小さい頃の朧げな記憶だけど、お母様がよくお父様にやってあげてたの。
なんでなのって聞いたら、疲れた時にしてもらうと元気になれるんだって言ってた。
だから、わたしもカカシにしてあげたくて。
しても、いいかな?」
「じゃあ、お言葉に甘えようかな」
珍しくカカシが照れていて、わたしもなんだか照れてしまう。
近くにあったソファに座ってカカシに横になってもらう。
膝にバスタオルを引こうとするとそのままがいいと言って、わたしのお腹の方に顔を向けてわたしの膝に頭を乗せる。
「……なんか照れるね。
耳そうじなんて、誰かにやってもらうの子供の時以来だよ……」
「そうだよね。
痛かったら言ってね」
「うん」
カカシの少しチクチクする銀髪を撫でて、そっと耳かきを入れる。
思った以上にドキドキするな。
「人にやってもらうのって、こんな気持ちーんだ……。
イッシン様の気持ち、わかったかも……」
「本当?よかった。
じゃあ、反対向いて貰っていい?」
するとカカシが一度立ち上がり、わたしをソファの反対の端に追いやる。
「こうした方が、すずらんにひっつけるから」
そう言ってわたしの膝にまた転がると、両手をわたしの体に巻きつける。
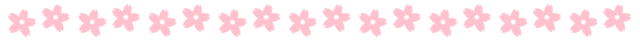
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする