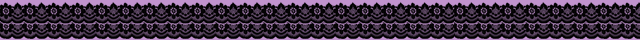
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
ハリー・ポッターと沈黙の天使
第22章 【パンドラの箱】
(――ああ、そうか。つまり、自分は全く相手にならないと言う訳だ――)
防衛術を学ぶ集会で突きつけられた戦力外通告。いつかこうなる日が来るんじゃないかと思っていたが、DAの集会を初めてまだ3回目。
時間になおすと1カ月弱しかたっていないにもかかわらず、この仕打ちはクリスを再び奈落の底に落とすのに十分だった。
「ああ、分かった。それじゃあ……私は別の人と組むよ」
「う、うん。ごめんね」
劣等生だったネビルに自信がつき、やる気になったことは良い事だ。クリスはなるべくそう言う風に見える表情を作ったが、本当に自分がそんな表情をしているのか自信がなかった。
クリスは壁際にあるクッションに座ると、授業中に復習している1年生用の呪文を、独り延々と繰り返し練習した。この時ほど、1時間という時間が長いと思ったことはなかった。
次の週から、クリスが人生で初めてクィディッチというスポーツに感謝したい出来事が起こった。
それはシーズン第1回戦目のグリフィンドール対スリザリンが近づいたことで、キャプテンのアンジェリーナが毎晩欠かさず練習をすると言って、DAの集会を止めさせたことだ。
集会に行っても身の置き所がなかったクリスにとっては、これはありがたかった。
しかし、これが全くありがたくなかった者がいた、他の誰でもない、ロンだ。
このシーズンになると、生徒同士で小競り合いが勃発し、あっちで鼻毛の伸びる呪いがかけられただの、こっちでニキビが膨れ上がる呪いがかけられただのてんやわんやんの大騒ぎになる。
今年で選手5年目のハリーは慣れたもので、どんな脅しをかけられても平気だったが、ロンはスリザリンのトロールみたいな選手に「おい、ウィーズリー。俺のブラッジャーでお前の髪より真っ赤な鼻血をぶちまけさせてやろうか?」と言われると、怒るよりも先に顔を青くしていた。
「安心しろ、ロン。試合が終われば全て杞憂に終わるさ」
試合当日の朝、クリスがクロワッサンを一口食べ、8つに切られたオレンジの皮をむきながら言った。
ロンの顔色は青を通り越して白くなり、血の気が全く見られなかった。そういえば1年生の頃ハリーも同じようなことになっていたと思いながら、クリスは事も無げに言った。
防衛術を学ぶ集会で突きつけられた戦力外通告。いつかこうなる日が来るんじゃないかと思っていたが、DAの集会を初めてまだ3回目。
時間になおすと1カ月弱しかたっていないにもかかわらず、この仕打ちはクリスを再び奈落の底に落とすのに十分だった。
「ああ、分かった。それじゃあ……私は別の人と組むよ」
「う、うん。ごめんね」
劣等生だったネビルに自信がつき、やる気になったことは良い事だ。クリスはなるべくそう言う風に見える表情を作ったが、本当に自分がそんな表情をしているのか自信がなかった。
クリスは壁際にあるクッションに座ると、授業中に復習している1年生用の呪文を、独り延々と繰り返し練習した。この時ほど、1時間という時間が長いと思ったことはなかった。
次の週から、クリスが人生で初めてクィディッチというスポーツに感謝したい出来事が起こった。
それはシーズン第1回戦目のグリフィンドール対スリザリンが近づいたことで、キャプテンのアンジェリーナが毎晩欠かさず練習をすると言って、DAの集会を止めさせたことだ。
集会に行っても身の置き所がなかったクリスにとっては、これはありがたかった。
しかし、これが全くありがたくなかった者がいた、他の誰でもない、ロンだ。
このシーズンになると、生徒同士で小競り合いが勃発し、あっちで鼻毛の伸びる呪いがかけられただの、こっちでニキビが膨れ上がる呪いがかけられただのてんやわんやんの大騒ぎになる。
今年で選手5年目のハリーは慣れたもので、どんな脅しをかけられても平気だったが、ロンはスリザリンのトロールみたいな選手に「おい、ウィーズリー。俺のブラッジャーでお前の髪より真っ赤な鼻血をぶちまけさせてやろうか?」と言われると、怒るよりも先に顔を青くしていた。
「安心しろ、ロン。試合が終われば全て杞憂に終わるさ」
試合当日の朝、クリスがクロワッサンを一口食べ、8つに切られたオレンジの皮をむきながら言った。
ロンの顔色は青を通り越して白くなり、血の気が全く見られなかった。そういえば1年生の頃ハリーも同じようなことになっていたと思いながら、クリスは事も無げに言った。
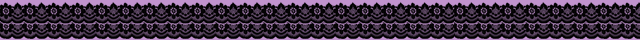
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする