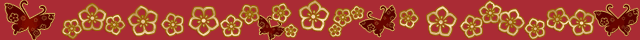
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
ナルシサス。【煉獄杏寿郎】
第12章 拾弐ノ型.焦がれる
「そんなものどうでもいい!!どうせ俺への恨み言だろう!」
「体を大切にしてほしい。杏寿郎が炭治郎に託した言葉はそれだけ。杏寿郎は貴方を尊敬こそすれ、恨んでなどいなかったのに。まだ、分からないのですか槇寿郎様...」
言って悲しそうに眉を下げる刹那の顔に、槇寿郎の瞳には死んだ妻・瑠火の顔が重なる。
初めて刹那を見た日、槇寿郎は妻が生き返ったのかと思った。
強い意志をもった真っ赤な瞳があまりにも酷似していて、それと同時に今の自分を見透かされているようで恐ろしかった。
この2年間刹那と目を合わせたのは、片手で足りるほどだったと思う。
極力会わず、関わらず。
槇寿郎は刹那を自分の領域に踏み入れさせなかった。
その瞳への畏怖故に。
『槇寿郎様。』
呼ばれ、俯いていた顔を上げそして息を飲む。
久方ぶりにしっかりと合わせた刹那の目に槇寿郎が感じていた恐ろしさなど微塵もなく
唯ひたすらに己の息子への深い慈愛だけが溢れている。
包み込むような、まるで御仏の前に居るような温かさ。
(ああ、杏寿郎...お前がこの子を気に入る理由が少し分かったかもしれない。)
酷く優しい紅。
その瞳の温かさに荒んでいた槇寿郎の心は徐々に解れ、唐突に理解する。
自分が息子に辛く当たっていた時、誰が側にいて、誰が息子に愛を与えていたのか。
息子の帰る場所になっていたのは誰だったのか。
(俺は、一体今まで何をしていたんだ...)
思い返してみれば酷い父親だ。
柱になるという事がどれだけ過酷な事か自分がよく分かっているくせに、酷い言葉を吐いた。
任務に行く度声をかけてくる真っ直ぐな己の息子が、今生死の境をさ迷っている。
それなのに自分は下の息子に当たり散らし、更には初対面の隊士や刹那にまで暴言を吐く有様。
どこで間違ったのか。
妻を失った自分と同様、子供達は母を失ったというのに。
何故もっと子供達のことを考えてやれなかったのか。
今更ながらに襲ってくる後悔と、息子を亡くすかもしれないという悲しみが槇寿郎の目から涙として溢れ出る。
「っ、杏寿郎....」
ぽつりと呟いた言葉。
ぼろぼろと泣く槇寿郎。
そこにはかつての優しい父の面影があった。
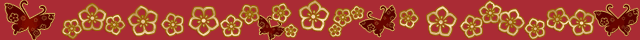
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする