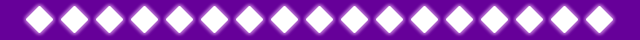
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
君は小生の宝物/葬儀屋/黒執事
第15章 その瞳の燐光
「!!ちょっ!先輩タンマ!!」
「あぁん!??」
この装置を壊されては大変だ。
リストに記載されてる1000人以上にも及ぶ魂の回収に加えてこんな数の動く死体を片付けながらその真相を調査など、無茶苦茶もいい所だ。
イライラするグレルの気持ちも分からなくはないが、ここはドルイットに装置を起動させなければ後々面倒だらけだ。
「フフ……これが本当の“力”というものだよ。ワイングラス1つで私は君らに勝利する事ができる!!ファハハハハハ!!」
「だんだんイライラしてきたんですが、殺してもよろしいですか?」
「いや待て、気持ちは分かるが……」
しばし静観していたセバスチャンも苛立ちを隠せない様だ。
だがその時……
ーガシャーーーン!!!ー
とうとう廊下の窓ガラスを割り、何十体もの動く死体がこのラウンジ内にまで押し寄せてきてしまった。
動きは決して素早くはないが、頭部の破壊以外の攻撃は無効で、何度も起き上がり向かってくるのだ。
「ちょっ…この数!まずいっしょ!!」
「子爵、早く装置を!!」
シエルが早く装置の起動をと訴えるが、ドルイットは至って涼しい表情だ。
「ノン!私はもう子爵ではない!!」
「………」
「“皇帝(カイザー)”…そう呼んでくれたら起動しよう。その雄駒鳥(コック・ロビン)のように愛らしいお口でね。」
自身が絶対的優位なポジションにいるのだと、挑発的なウインクを飛ばすドルイット。
「やっぱり今すぐ殺そう。」
「お待ち下さい。お気持ちは分かりますが…」
その態度にシエルも苛立ち出した様だ。
「おーう!我が身を賭けて命を散らす剣闘士達、さながら此処は背徳のコロッセウム!眼下を眺めワインをくゆらす私は皇帝ネロのごとしッ!!!」
完全に悦に入っているドルイット。
この状況でこんな台詞を吐くなど、ある意味人間離れした思考回路だ。
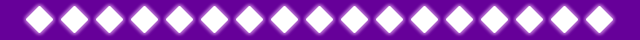
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする