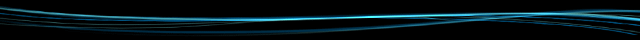
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
モデルのボーダー隊員~番外編~
第12章 女の子の日になったら
「いた...」
色々な僕を呼ぶ声が頭に響く。静かにして...。
「...陽介、保健室で湯たんぽ貰ってこい」
「お、おう。わかった」
「蓮琉は明希の背中を摩ってやれ。烏丸と出水は待機」
「待機かよ」
何か察したらしい秀ちゃんが的確に指示を出す。生理痛だと気付いたようだ。
「明希、痛むのは腹だけか?頭は痛くないか?」
「大丈夫...お腹だけ...」
「わかった。ありがとう」
廊下からバタバタと騒がしい足音が聞こえてきたかと思うと、勢いよくドアが開かれて陽介君が入ってきた。
「湯たんぽ!貰ってきたぞ!」
「ありがとう。明希、これを腹に当てろ」
「ん...ありがと...」
それから10分ほどが過ぎただろうか、痛みが和らぎ、立てるくらいには回復した。
「もう大丈夫。みんなありがとう」
「急にしゃがみこむからどうしたのかと思ったぜ」
「ごめんね。急に痛くなったから僕もびっくりしちゃった」
「そんな時もあるから仕方ないだろう。それより、出水が気付かなかったことに疑問が残るんだが」
公平君にはお姉さんがいる。だからそういう話も聞くことがあるんじゃないだろうか、というのが秀ちゃんの見解らしい。
「俺ん家の女の人はそういった痛みは無いっぽいからさ、全く気付かなかった」
「個人差があるらしいんで仕方ないっすよ。明希先輩は酷いみたいですし、我慢しないでください」
「さ!そろそろ帰ろうぜ!校門が閉まっちまう」
「そうだね。帰ろうか」
「姉さん。荷物は俺が持つ」
教室を出てからはずっと模擬戦やらランク戦やらの話が続いた。次こそはA級1位から落としてやる、やれるものならやってみろ、醜い争いっすね、だな、と賑やかに帰宅した。
玉狛に戻って、荷物を片付ける。制服を脱ぎ、部屋着に着替えてリビングに入ると、悠一が心配そうな顔でこっちに近づいてきた。
「大丈夫か?」
「うん、今は大丈夫。心配しないでね」
「いやいや、心配するから。レイジさんに頼んで今日のご飯は温かいものにしてもらったから」
「そうなんだ。ありがとう」
「どういたしまして。さ、ご飯が出来るまで暖かくしてような」
悠一に手を引かれ、ソファに座る悠一の膝の上に座る。その上から毛布を掛けてポカポカだ。
「暖かい」
「それは良かった」
ご飯が出来上がり、レイジさんが呼びに来た時には2人とも夢の中だったとかなんとか。
色々な僕を呼ぶ声が頭に響く。静かにして...。
「...陽介、保健室で湯たんぽ貰ってこい」
「お、おう。わかった」
「蓮琉は明希の背中を摩ってやれ。烏丸と出水は待機」
「待機かよ」
何か察したらしい秀ちゃんが的確に指示を出す。生理痛だと気付いたようだ。
「明希、痛むのは腹だけか?頭は痛くないか?」
「大丈夫...お腹だけ...」
「わかった。ありがとう」
廊下からバタバタと騒がしい足音が聞こえてきたかと思うと、勢いよくドアが開かれて陽介君が入ってきた。
「湯たんぽ!貰ってきたぞ!」
「ありがとう。明希、これを腹に当てろ」
「ん...ありがと...」
それから10分ほどが過ぎただろうか、痛みが和らぎ、立てるくらいには回復した。
「もう大丈夫。みんなありがとう」
「急にしゃがみこむからどうしたのかと思ったぜ」
「ごめんね。急に痛くなったから僕もびっくりしちゃった」
「そんな時もあるから仕方ないだろう。それより、出水が気付かなかったことに疑問が残るんだが」
公平君にはお姉さんがいる。だからそういう話も聞くことがあるんじゃないだろうか、というのが秀ちゃんの見解らしい。
「俺ん家の女の人はそういった痛みは無いっぽいからさ、全く気付かなかった」
「個人差があるらしいんで仕方ないっすよ。明希先輩は酷いみたいですし、我慢しないでください」
「さ!そろそろ帰ろうぜ!校門が閉まっちまう」
「そうだね。帰ろうか」
「姉さん。荷物は俺が持つ」
教室を出てからはずっと模擬戦やらランク戦やらの話が続いた。次こそはA級1位から落としてやる、やれるものならやってみろ、醜い争いっすね、だな、と賑やかに帰宅した。
玉狛に戻って、荷物を片付ける。制服を脱ぎ、部屋着に着替えてリビングに入ると、悠一が心配そうな顔でこっちに近づいてきた。
「大丈夫か?」
「うん、今は大丈夫。心配しないでね」
「いやいや、心配するから。レイジさんに頼んで今日のご飯は温かいものにしてもらったから」
「そうなんだ。ありがとう」
「どういたしまして。さ、ご飯が出来るまで暖かくしてような」
悠一に手を引かれ、ソファに座る悠一の膝の上に座る。その上から毛布を掛けてポカポカだ。
「暖かい」
「それは良かった」
ご飯が出来上がり、レイジさんが呼びに来た時には2人とも夢の中だったとかなんとか。
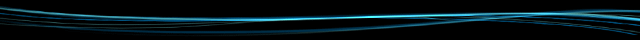
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする