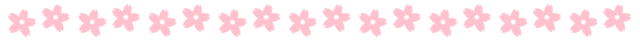
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【忍たま】短編集
第3章 ただそれだけを(立花仙蔵)
「椿いいか、約束する。私は必ず戻って来る。お前がこれを持ち続ける限り、私はいつでも椿の側にいる。」
私の心を見透かすように仙蔵が言葉をくれる。
離れていても大丈夫だと、信じれる言葉。
「うん、いつまでも待ってる。仙蔵のこと、信じてるね。」
満足そうに微笑むと、仙蔵はまた私を抱き締める。
彼の背に手を伸ばし、私も仙蔵に答える。
この瞬間を惜しむように、二人でお互いの形を確かめ合った。
仙蔵たちが巣立った後も慌ただしい日が続き、学園長の思いつきも手伝って忙しさが寂しさを紛らわせてくれた。
会えなくても離れていても、このつげの櫛があれば仙蔵を側に感じることができた。
彼が学園を卒業してまもなく二度目の桜の季節がやって来る。
その日椿は、一人で町の仕立て屋に訪れていた。
この仕立て屋、都築屋には椿と同じ年の頃の若旦那がいて、彼女が顔を出すと人の良さそうな顔で近寄ってくるのだった。
若旦那が椿を気に入っていることは周囲の目には明らかだった。
ただ残念なことに、当の本人はまるでそのことに気付いていない。
「椿さん!いらっしゃい。」
「こんにちは。この前お願いしていたもの、できてますか?」
「あ、はい。こちらですね。寸法直してみましたので、こちらでご確認下さい。」
若旦那は椿を奥にある鏡の前へ案内する。
手直しされた着物を広げ、椿の肩にかけて長さを確かめる。
「わぁ、丁度良さそうですね。流石です。」
椿は自分のサイズに直った着物を嬉しそうに見ていた。
若旦那は彼女の肩越しに、鏡に映る椿を見て呟く。
「……綺麗だ。」
「え?うーん、落ち着きのある色合いではありますね。」
椿のことを言ったのだが、彼女は着物を誉められたと勘違いしている。
実際椿が持ってきた着物は、知り合いのおばさんから譲って貰ったというもので彼女が着るには地味ではあった。
若旦那は椿の発言に苦笑し、それ以上は何も言えなかった。
私の心を見透かすように仙蔵が言葉をくれる。
離れていても大丈夫だと、信じれる言葉。
「うん、いつまでも待ってる。仙蔵のこと、信じてるね。」
満足そうに微笑むと、仙蔵はまた私を抱き締める。
彼の背に手を伸ばし、私も仙蔵に答える。
この瞬間を惜しむように、二人でお互いの形を確かめ合った。
仙蔵たちが巣立った後も慌ただしい日が続き、学園長の思いつきも手伝って忙しさが寂しさを紛らわせてくれた。
会えなくても離れていても、このつげの櫛があれば仙蔵を側に感じることができた。
彼が学園を卒業してまもなく二度目の桜の季節がやって来る。
その日椿は、一人で町の仕立て屋に訪れていた。
この仕立て屋、都築屋には椿と同じ年の頃の若旦那がいて、彼女が顔を出すと人の良さそうな顔で近寄ってくるのだった。
若旦那が椿を気に入っていることは周囲の目には明らかだった。
ただ残念なことに、当の本人はまるでそのことに気付いていない。
「椿さん!いらっしゃい。」
「こんにちは。この前お願いしていたもの、できてますか?」
「あ、はい。こちらですね。寸法直してみましたので、こちらでご確認下さい。」
若旦那は椿を奥にある鏡の前へ案内する。
手直しされた着物を広げ、椿の肩にかけて長さを確かめる。
「わぁ、丁度良さそうですね。流石です。」
椿は自分のサイズに直った着物を嬉しそうに見ていた。
若旦那は彼女の肩越しに、鏡に映る椿を見て呟く。
「……綺麗だ。」
「え?うーん、落ち着きのある色合いではありますね。」
椿のことを言ったのだが、彼女は着物を誉められたと勘違いしている。
実際椿が持ってきた着物は、知り合いのおばさんから譲って貰ったというもので彼女が着るには地味ではあった。
若旦那は椿の発言に苦笑し、それ以上は何も言えなかった。
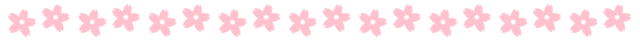
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする