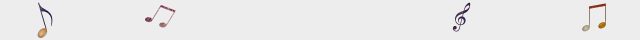
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
〖 IDOLiSH7 〗 なないろパレット
第11章 スタートライン
小「愛聖さん、着いたよ?」
事務所へ戻る車でいつの間にか眠ってしまっていたらしく、社長に呼びかけられてハッと目を開ける。
『すみません···こんな時に眠ってしまうとか』
シートベルトを外しながら言えば、社長は大丈夫だからと笑う。
小「いろいろな事が起きたんだから、こんな時くらい眠れる時に寝といた方がいいよ~?昨夜だって寝付けなかったんじゃない?···あ、もしかして万理くんが寝かしてくれなかったとか?」
クスクスと笑いながら言う社長が、自分のシートベルトを外しながら私を振り返る。
『社長···それセクハラギリギリアウトですよ?それに、万理はそんな飢えたオオカミさんじゃありませんから』
···多分、と付け加えれば、それを聞いて社長がまた笑った。
小「万理くんもあんなイケメンなのに、浮いたウワサのひとつも聞かないほど仕事人間だから、僕はちょっと心配しちゃうよ」
『万理が仕事人間なのは、社長の事が大好きだからじゃないですか?』
小「ん~、そうかも?僕もまだ隅には置けない感じ?」
『まだまだ、大丈夫だと思いますよ?』
不穏な気持ちを払うように社長が気を使ってくれてるのが分かり、冗談混じりの会話をしながら車を降りた。
『あっ···』
小「···っと!」
社長の後について事務所のドアの前に立った時、ザワっとした風が吹き抜け、被っていた帽子を飛ばして不揃いの髪を靡かせる。
小「ナイスキャッチ、だね。はい、愛聖さん?」
『ありがとうございます···』
片手で髪を押さえながら、空いている手で社長から帽子を受け取り、ガラスを鏡代わりにしながら髪を束ね込み、また帽子を被る。
『なんだかこれじゃ私が、犯人みたいですね』
ガラスに映る自分は、帽子を深く被り、顔半分が隠れるような大きなマスクをして···今日の事情によりメイクさえほとんどないような格好で。
そんな姿から目を逸らし俯く私の肩に、社長がそっと手を置いた。
小「大丈夫。愛聖さんは堂々としていなさい···今はまだ難しい話かも知れないけど、背筋を伸ばして前を向いていなさい。八乙女に負けないくらい、僕がちゃんと···綺麗にしてあげるから」
その髪は、八乙女がそうしなさいって言って伸ばしていたんでしょ?
社長はそう続けて、いつもの様に穏やかな微笑みを浮かべた。
事務所へ戻る車でいつの間にか眠ってしまっていたらしく、社長に呼びかけられてハッと目を開ける。
『すみません···こんな時に眠ってしまうとか』
シートベルトを外しながら言えば、社長は大丈夫だからと笑う。
小「いろいろな事が起きたんだから、こんな時くらい眠れる時に寝といた方がいいよ~?昨夜だって寝付けなかったんじゃない?···あ、もしかして万理くんが寝かしてくれなかったとか?」
クスクスと笑いながら言う社長が、自分のシートベルトを外しながら私を振り返る。
『社長···それセクハラギリギリアウトですよ?それに、万理はそんな飢えたオオカミさんじゃありませんから』
···多分、と付け加えれば、それを聞いて社長がまた笑った。
小「万理くんもあんなイケメンなのに、浮いたウワサのひとつも聞かないほど仕事人間だから、僕はちょっと心配しちゃうよ」
『万理が仕事人間なのは、社長の事が大好きだからじゃないですか?』
小「ん~、そうかも?僕もまだ隅には置けない感じ?」
『まだまだ、大丈夫だと思いますよ?』
不穏な気持ちを払うように社長が気を使ってくれてるのが分かり、冗談混じりの会話をしながら車を降りた。
『あっ···』
小「···っと!」
社長の後について事務所のドアの前に立った時、ザワっとした風が吹き抜け、被っていた帽子を飛ばして不揃いの髪を靡かせる。
小「ナイスキャッチ、だね。はい、愛聖さん?」
『ありがとうございます···』
片手で髪を押さえながら、空いている手で社長から帽子を受け取り、ガラスを鏡代わりにしながら髪を束ね込み、また帽子を被る。
『なんだかこれじゃ私が、犯人みたいですね』
ガラスに映る自分は、帽子を深く被り、顔半分が隠れるような大きなマスクをして···今日の事情によりメイクさえほとんどないような格好で。
そんな姿から目を逸らし俯く私の肩に、社長がそっと手を置いた。
小「大丈夫。愛聖さんは堂々としていなさい···今はまだ難しい話かも知れないけど、背筋を伸ばして前を向いていなさい。八乙女に負けないくらい、僕がちゃんと···綺麗にしてあげるから」
その髪は、八乙女がそうしなさいって言って伸ばしていたんでしょ?
社長はそう続けて、いつもの様に穏やかな微笑みを浮かべた。
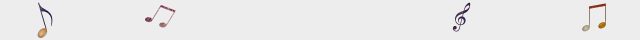
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする