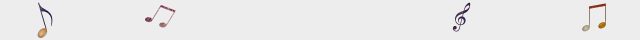
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
〖 IDOLiSH7 〗 なないろパレット
第11章 スタートライン
特別大きな事務所ではないと普段から社長が笑いながら言ってはいても、それなりにきちんとした芸能プロダクションなんだから、その可能性は充分にある。
八乙女プロダクションのように、一晩中ずっと明かりがついていて人の出入りがある訳ではなく、社長が他の社員がいざという時にちゃんと仕事が出来るように、特に急ぎの仕事がなければ定時退社を推奨してるから、これまでそういった事案がなかった事の方が奇跡に近い。
定時退勤を押して残ってるのは、万理くらいだし。
だとしたら、どうしてこのタイミングで?
そこまで考えて、ふと···気付く。
それよりも、もし···昨日の人たちが、とか。
そう思い出すと、自分の思考がフリーズしていくのを感じる。
もし···昨日の···
「···さん?···佐伯さん、大丈夫ですか?」
壁にもたれ掛かる私を気にしてか、近くにいた事務員さんが声を掛けてくる。
『あ···すみません、大丈夫です』
「でも、なんだか顔色が悪いような···ほんとに大丈夫ですか?気分が悪いようだったら、社長か大神さんを···あ、ちょうど出て来たようなので呼んできます」
顔を上げれば、目線の先には難しい顔をした社長たちがドアから出て来たところに事務員さんが声を掛ける場面が見える。
いくつか言葉を交わした後、万理が足早に近寄って屈みこんだ。
万「愛聖、どうした?」
『万理···どうしよう···もしかしてこれも···』
万「大丈夫、いまはそんな心配はしなくていいから」
『だけど···』
万「愛聖、とりあえず落ち着いて。そうだ、車の中に移動しよう···社長、いいですよね?」
万理が後ろに立つ社長を振り返っていえば、社長は目線だけで小さく頷いた。
万「立てる?もし無理そうなら手を貸すけど」
大丈夫、と返事をする前に既に万理は私を支えてくれていて。
万「俺はここの事があるから一緒に行けないけど、でも、事情が分かってる社長が同行するから···」
そう言いながら私を車へ乗せ、万理はドアを閉めた。
小「万理くん、後のことは頼むよ」
ひとことそう告げて万理が了解すると、社長はゆっくりと車を走らせた。
八乙女プロダクションのように、一晩中ずっと明かりがついていて人の出入りがある訳ではなく、社長が他の社員がいざという時にちゃんと仕事が出来るように、特に急ぎの仕事がなければ定時退社を推奨してるから、これまでそういった事案がなかった事の方が奇跡に近い。
定時退勤を押して残ってるのは、万理くらいだし。
だとしたら、どうしてこのタイミングで?
そこまで考えて、ふと···気付く。
それよりも、もし···昨日の人たちが、とか。
そう思い出すと、自分の思考がフリーズしていくのを感じる。
もし···昨日の···
「···さん?···佐伯さん、大丈夫ですか?」
壁にもたれ掛かる私を気にしてか、近くにいた事務員さんが声を掛けてくる。
『あ···すみません、大丈夫です』
「でも、なんだか顔色が悪いような···ほんとに大丈夫ですか?気分が悪いようだったら、社長か大神さんを···あ、ちょうど出て来たようなので呼んできます」
顔を上げれば、目線の先には難しい顔をした社長たちがドアから出て来たところに事務員さんが声を掛ける場面が見える。
いくつか言葉を交わした後、万理が足早に近寄って屈みこんだ。
万「愛聖、どうした?」
『万理···どうしよう···もしかしてこれも···』
万「大丈夫、いまはそんな心配はしなくていいから」
『だけど···』
万「愛聖、とりあえず落ち着いて。そうだ、車の中に移動しよう···社長、いいですよね?」
万理が後ろに立つ社長を振り返っていえば、社長は目線だけで小さく頷いた。
万「立てる?もし無理そうなら手を貸すけど」
大丈夫、と返事をする前に既に万理は私を支えてくれていて。
万「俺はここの事があるから一緒に行けないけど、でも、事情が分かってる社長が同行するから···」
そう言いながら私を車へ乗せ、万理はドアを閉めた。
小「万理くん、後のことは頼むよ」
ひとことそう告げて万理が了解すると、社長はゆっくりと車を走らせた。
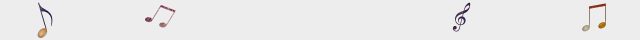
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする