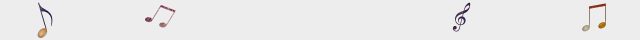
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
〖 IDOLiSH7 〗 なないろパレット
第11章 スタートライン
差し出した手に、戸惑いながらもそっと重ねて来る小さな手。
その手を迷うことなくキュッと握れば、愛聖もゆっくり握り返してくる。
「眠れないなら、少しだけ···昔話をしてあげるよ。もちろん、眠くなったら寝ちゃっていいからね?」
コクン、と頷く愛聖を見て、そう遠くはない昔話を始める。
「むかしむかし、ある所に···音楽が好きで、カッコイイ万理くんという人がいました···あ、コラ、そこ笑うとこじゃないから」
自分を題材にした昔話を初めてすぐに、愛聖がフッと笑いを漏らす。
「バンドを組み音楽をやりながらも、それを続ける為にバイトを掛け持ちしながらひとり暮らしをして···そんな時、1人の女の子に出会いました」
『それ···私のこと?』
まだ潤んだままの目を軽く擦りながら、愛聖が言うけど、昔話だから静かに聞いててね?と返して、また話を続けた。
「引越しの挨拶の時に隣の部屋にお母さんと2人で住んでいるのは知ってたし、見かける度に声を掛けてはいたけど逃げられちゃったりして。もしかして怪しい人だと思われてるんじゃ···と悲しくなる時もありました。そんな、ある日···」
あの日はバイト中に体調が悪くなって早退すると、隣の家の前に愛聖がランドセルを抱えて座ってて。
状況から見て、鍵を失くしたか忘れて学校に行ってしまったかだろうとは思いつつも声を掛ければ、顔を背けたままなんでもない!を繰り返すし。
だから俺は、つい、聞いてしまったんだ。
「あのさ?前からずっと思ってたんだけど···もしかして俺のこと、嫌い?」
通路に膝をついて目線を合わせようとしても、顔を背けたまま、首だけを横に振って答える。
「じゃあ···怖いとか?」
それにも首だけを振って答える。
「う~ん···参ったな···」
これ以上ムリになにかを聞き出そうとしても逆効果だし···でも、こんな所に女の子を1人で置いとくにも···
そう思い始めた時、鍵を忘れちゃって家に入れないんだとポツリポツリと話し出してくれて。
それを聞いて、俺の部屋からタオルやら毛布やらを持ち出してグルグル巻きにして、愛聖の母さんが帰るのを一緒に外で待ってたっけ。
その結果、俺はその夜から熱が上がって寝込む事には
なったけど。
その手を迷うことなくキュッと握れば、愛聖もゆっくり握り返してくる。
「眠れないなら、少しだけ···昔話をしてあげるよ。もちろん、眠くなったら寝ちゃっていいからね?」
コクン、と頷く愛聖を見て、そう遠くはない昔話を始める。
「むかしむかし、ある所に···音楽が好きで、カッコイイ万理くんという人がいました···あ、コラ、そこ笑うとこじゃないから」
自分を題材にした昔話を初めてすぐに、愛聖がフッと笑いを漏らす。
「バンドを組み音楽をやりながらも、それを続ける為にバイトを掛け持ちしながらひとり暮らしをして···そんな時、1人の女の子に出会いました」
『それ···私のこと?』
まだ潤んだままの目を軽く擦りながら、愛聖が言うけど、昔話だから静かに聞いててね?と返して、また話を続けた。
「引越しの挨拶の時に隣の部屋にお母さんと2人で住んでいるのは知ってたし、見かける度に声を掛けてはいたけど逃げられちゃったりして。もしかして怪しい人だと思われてるんじゃ···と悲しくなる時もありました。そんな、ある日···」
あの日はバイト中に体調が悪くなって早退すると、隣の家の前に愛聖がランドセルを抱えて座ってて。
状況から見て、鍵を失くしたか忘れて学校に行ってしまったかだろうとは思いつつも声を掛ければ、顔を背けたままなんでもない!を繰り返すし。
だから俺は、つい、聞いてしまったんだ。
「あのさ?前からずっと思ってたんだけど···もしかして俺のこと、嫌い?」
通路に膝をついて目線を合わせようとしても、顔を背けたまま、首だけを横に振って答える。
「じゃあ···怖いとか?」
それにも首だけを振って答える。
「う~ん···参ったな···」
これ以上ムリになにかを聞き出そうとしても逆効果だし···でも、こんな所に女の子を1人で置いとくにも···
そう思い始めた時、鍵を忘れちゃって家に入れないんだとポツリポツリと話し出してくれて。
それを聞いて、俺の部屋からタオルやら毛布やらを持ち出してグルグル巻きにして、愛聖の母さんが帰るのを一緒に外で待ってたっけ。
その結果、俺はその夜から熱が上がって寝込む事には
なったけど。
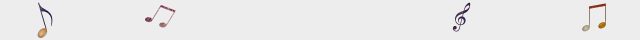
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする