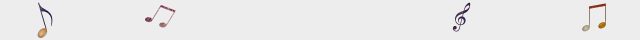
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
〖 IDOLiSH7 〗 なないろパレット
第11章 スタートライン
「まさかの隣同士···」
2組の布団が、少し離されてはいても隣同士に並べて敷かれていた。
『社長が···万理なら信用できるからって』
いや、そのやり取りはさっきもしたけどホントにそう来たか···と。
「俺は別にいいけど、愛聖が落ち着かないんじゃ···」
俺がそう言えば愛聖は何度か瞬きをしてから、1人でいるよりは安心だからと返してきた。
「そっか、それならもう布団入っちゃおう。明日は色々と忙しくなるみたいだし、ゆっくりと休むのも必要だからね」
愛聖が布団に入るのを見守って、部屋の灯りを落とす。
真っ暗にするのは怖いだろうから、部屋の中が薄ら見える位の明るさまで、だけど。
『おやすみなさい』
「おやすみ愛聖」
ごく当たり前の挨拶を交わして、自分も布団へと入る。
せめて愛聖が先に寝付いてから眠ろう。
そう思って様子を見ながら静かな時間を過ごしても、愛聖が寝付く様子を感じられず、どれくらいの時間が経ったのか、気が付けば愛聖は声を押し殺すようにして静かに泣いていた。
声を掛けるべきか、それとも気が付かないフリを突き通すべきか···迷う。
あんな風にしているって事は、泣いてる事を知られたくないからだろうし。
かと言って、なにもアクションを起こさずにいるのは俺がイヤだ。
じゃあ、なんて声を掛ける?
それとも、声を掛けなくても安心させてやれる事があるか?
あ···これなら···
掛け布団の隙間から腕を伸ばし、そっと愛聖の頭を撫でてみる。
俺の手が触れた瞬間はピクリと肩を跳ねさせてはいたけど、何度も、何度も、ゆっくりと頭を撫でていると、その小さな肩がコロンと向きを変え、愛聖が俺を見た。
『万理···』
なにかを言おうとする言葉を遮るように、軽くおでこをつついて微笑んでみせる。
「こんばんは。いつかの···寂しがり屋のネコさん」
愛聖が寮に入る事になって、俺の家で過ごす最後の夜のことを思い出し、そう呼んでみる。
「今夜は歌を聞かせてあげる事は出来ないけど、でも···これなら寂しくないだろ?」
頭を撫でていた手を離し、伸ばした手を愛聖へ開いた。
「眠るまでずっと、繋いでいてあげるから」
2組の布団が、少し離されてはいても隣同士に並べて敷かれていた。
『社長が···万理なら信用できるからって』
いや、そのやり取りはさっきもしたけどホントにそう来たか···と。
「俺は別にいいけど、愛聖が落ち着かないんじゃ···」
俺がそう言えば愛聖は何度か瞬きをしてから、1人でいるよりは安心だからと返してきた。
「そっか、それならもう布団入っちゃおう。明日は色々と忙しくなるみたいだし、ゆっくりと休むのも必要だからね」
愛聖が布団に入るのを見守って、部屋の灯りを落とす。
真っ暗にするのは怖いだろうから、部屋の中が薄ら見える位の明るさまで、だけど。
『おやすみなさい』
「おやすみ愛聖」
ごく当たり前の挨拶を交わして、自分も布団へと入る。
せめて愛聖が先に寝付いてから眠ろう。
そう思って様子を見ながら静かな時間を過ごしても、愛聖が寝付く様子を感じられず、どれくらいの時間が経ったのか、気が付けば愛聖は声を押し殺すようにして静かに泣いていた。
声を掛けるべきか、それとも気が付かないフリを突き通すべきか···迷う。
あんな風にしているって事は、泣いてる事を知られたくないからだろうし。
かと言って、なにもアクションを起こさずにいるのは俺がイヤだ。
じゃあ、なんて声を掛ける?
それとも、声を掛けなくても安心させてやれる事があるか?
あ···これなら···
掛け布団の隙間から腕を伸ばし、そっと愛聖の頭を撫でてみる。
俺の手が触れた瞬間はピクリと肩を跳ねさせてはいたけど、何度も、何度も、ゆっくりと頭を撫でていると、その小さな肩がコロンと向きを変え、愛聖が俺を見た。
『万理···』
なにかを言おうとする言葉を遮るように、軽くおでこをつついて微笑んでみせる。
「こんばんは。いつかの···寂しがり屋のネコさん」
愛聖が寮に入る事になって、俺の家で過ごす最後の夜のことを思い出し、そう呼んでみる。
「今夜は歌を聞かせてあげる事は出来ないけど、でも···これなら寂しくないだろ?」
頭を撫でていた手を離し、伸ばした手を愛聖へ開いた。
「眠るまでずっと、繋いでいてあげるから」
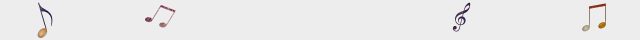
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする