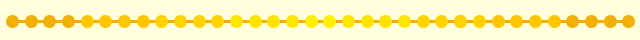
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【FF7 ヴィンセント BL】ご飯が炊けるまで
第1章 1
炊飯器に米を計って入れ、水を入れて研ぎ、目盛まで浸して、スイッチを入れる。鍋にパウチを入れて水を張っておき、食器棚から大皿を二枚出して、スプーンを用意し、グラスに水を注いだ。
あとは炊き上がりを待つだけだ。
テーブルへゆき、ヴィンセントの向かいに掛けた。
「40分くらいで炊けるから」
ヴィンセントが、読んでいた雑誌を閉じる。
「ありがとう」
そう言ってまた微笑む。…本当に、綺麗な貌だ。
長い睫毛に縁取られた赫い赫い目。
整った鼻梁。顔を傾げるとさらさら流れる髪。
…形の良い唇は、今は見ないようにしておこう。
でも一番好きなこの赫い目は見つめてても良いんだ、僕は彼の恋人なんだから…。
少しの間、見つめ合っていたが、ヴィンセントが軽く吹き出すように笑った。
「え、なに」
「寝グセがすごい」
「えっ、」
頭に手をやるとすぐに、跳ねた髪が掌に当たった。
ヴィンセントは口許を手で覆いながら笑い声で続ける。
「前髪も…」
リオがしかめ面をしながら手を額の方へ回すと、なるほど重力を気にしていないかのような髪型になっているようだ。
「さっきキスしたくせに、」
なんで今まで言わないんだ、と睨むと、少し困ったような顔をした。
「そのままでいいと思ったんだ。おまえが…その、…可愛いというか、愛おしいと…思った」
リオは不意を突かれたようで、頬を染め、また唇を尖らせる。
無自覚なのだろうか。
そんな顔をされるとヴィンセントはその唇を奪いたい衝動に駆られる。
昼寝のあいだ中、リオはヴィンセントの肩に額をうずめていた。前髪はそれで上を向いたままになり、腕枕に擦り付けていた後ろ髪も逆巻いたのだろう。
それがヴィンセントにはどうしようもなく愛おしかった。
あの髪をくしゃくしゃにして口付けたい。それから…。
気を落ち着けようと、静かに息を吐く。
「今日はもう出掛けないし、私しか居ないのだからいいだろう。…気になるなら蒸しタオルを当ててやろうか、ご飯が炊けるまで」
ヴィンセントのフォローに、リオはこっくりと頷き、
「髪を短くしてから、すぐ寝グセがつくようになった」
言い訳とも文句ともつかない言葉を零す。
タオルを取りに洗面所へ向かいながら、あの柔らかな短い髪に指を通せば、またキスをしないではいられないだろう、とヴィンセントは予感した。
了
あとは炊き上がりを待つだけだ。
テーブルへゆき、ヴィンセントの向かいに掛けた。
「40分くらいで炊けるから」
ヴィンセントが、読んでいた雑誌を閉じる。
「ありがとう」
そう言ってまた微笑む。…本当に、綺麗な貌だ。
長い睫毛に縁取られた赫い赫い目。
整った鼻梁。顔を傾げるとさらさら流れる髪。
…形の良い唇は、今は見ないようにしておこう。
でも一番好きなこの赫い目は見つめてても良いんだ、僕は彼の恋人なんだから…。
少しの間、見つめ合っていたが、ヴィンセントが軽く吹き出すように笑った。
「え、なに」
「寝グセがすごい」
「えっ、」
頭に手をやるとすぐに、跳ねた髪が掌に当たった。
ヴィンセントは口許を手で覆いながら笑い声で続ける。
「前髪も…」
リオがしかめ面をしながら手を額の方へ回すと、なるほど重力を気にしていないかのような髪型になっているようだ。
「さっきキスしたくせに、」
なんで今まで言わないんだ、と睨むと、少し困ったような顔をした。
「そのままでいいと思ったんだ。おまえが…その、…可愛いというか、愛おしいと…思った」
リオは不意を突かれたようで、頬を染め、また唇を尖らせる。
無自覚なのだろうか。
そんな顔をされるとヴィンセントはその唇を奪いたい衝動に駆られる。
昼寝のあいだ中、リオはヴィンセントの肩に額をうずめていた。前髪はそれで上を向いたままになり、腕枕に擦り付けていた後ろ髪も逆巻いたのだろう。
それがヴィンセントにはどうしようもなく愛おしかった。
あの髪をくしゃくしゃにして口付けたい。それから…。
気を落ち着けようと、静かに息を吐く。
「今日はもう出掛けないし、私しか居ないのだからいいだろう。…気になるなら蒸しタオルを当ててやろうか、ご飯が炊けるまで」
ヴィンセントのフォローに、リオはこっくりと頷き、
「髪を短くしてから、すぐ寝グセがつくようになった」
言い訳とも文句ともつかない言葉を零す。
タオルを取りに洗面所へ向かいながら、あの柔らかな短い髪に指を通せば、またキスをしないではいられないだろう、とヴィンセントは予感した。
了
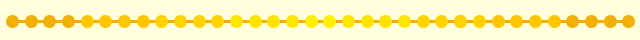
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする