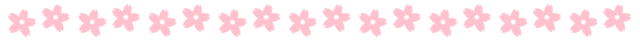
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【HQ】繋がる縁の円
第11章 裏で動いた恋模様
‐きとりside‐
無理に明るく笑って仕事をしていると、疲労感は倍以上で。
疲れ果てて終了した仕事。
ご飯も食べないで、シャワー浴びて寝てしまいたい。
だけど、家に帰ると赤葦が居る。
話の続きを、この状態で聞くのは酷である。
それでも、帰らないとシャワーも布団も無い訳で。
諦めて家に戻った。
扉を開けた瞬間に、家の中から漂う香ばしい匂い。
ちょっと焦げた、醤油の匂いだ。
食事も要らないと思っていたけど、この匂いには弱い。
これは、日本人の本能だと思う。
誘われるように、フラフラと台所へ歩いていった。
そこには、赤葦が立っていて、私に気付いたのか振り返る。
片手に、フライパンを持っていた。
「おかえりなさい。」
「た、ただいま。」
私にとっては、目の前で起きている事が現実から掛け離れている。
それなのに、出迎える挨拶は、あまりに普通過ぎて目を瞬かせた。
「どうかしましたか。」
「いや、あの。赤葦って料理出来んだな、って。驚いて。」
「出来なくは無いですよ。」
赤葦の視線は、すぐにフライパンの方に戻って、その中身を箸で混ぜながら会話をしている。
喋りながら作業が出来るなら、それなりに慣れた事なんだろう。
作業の邪魔にならないように、その場を離れて風呂場に向かった。
無理に明るく笑って仕事をしていると、疲労感は倍以上で。
疲れ果てて終了した仕事。
ご飯も食べないで、シャワー浴びて寝てしまいたい。
だけど、家に帰ると赤葦が居る。
話の続きを、この状態で聞くのは酷である。
それでも、帰らないとシャワーも布団も無い訳で。
諦めて家に戻った。
扉を開けた瞬間に、家の中から漂う香ばしい匂い。
ちょっと焦げた、醤油の匂いだ。
食事も要らないと思っていたけど、この匂いには弱い。
これは、日本人の本能だと思う。
誘われるように、フラフラと台所へ歩いていった。
そこには、赤葦が立っていて、私に気付いたのか振り返る。
片手に、フライパンを持っていた。
「おかえりなさい。」
「た、ただいま。」
私にとっては、目の前で起きている事が現実から掛け離れている。
それなのに、出迎える挨拶は、あまりに普通過ぎて目を瞬かせた。
「どうかしましたか。」
「いや、あの。赤葦って料理出来んだな、って。驚いて。」
「出来なくは無いですよ。」
赤葦の視線は、すぐにフライパンの方に戻って、その中身を箸で混ぜながら会話をしている。
喋りながら作業が出来るなら、それなりに慣れた事なんだろう。
作業の邪魔にならないように、その場を離れて風呂場に向かった。
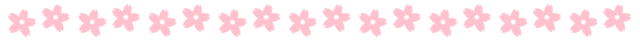
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする