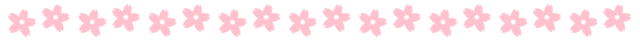
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【HQ】繋がる縁の円
第11章 裏で動いた恋模様
‐きとりside‐
今の、りらを神格化しているのが間違いじゃないのなら。
赤葦の私に対する気持ちは、多分ホンモノじゃない。
神様の傍に居られる手段として、私を好きになろうとするんだ。
「きとりさん、失礼な事を考えてませんか。」
「…え?何が?」
確かに人の気持ちを疑うなんて、失礼な事だけど。
それを読まれるとは思わなかった。
盛大な溜め息を吐いてから、私を真剣に見詰める眼が怖い。
「…俺、正直に言うと。昔は貴女と付き合えば、恋人から結婚まで持っていければ、りらの傍に居られると、思ってました。」
今は違うと、理由まで含めて話してくれようとしている。
こういう、面倒なのは嫌いな筈なのに、理解が追い付かない私の為に。
それなら、私も真剣に受け止めてやらないといけない。
息を飲んで、次の言葉を待とうとした時…。
目覚まし時計が、音を立てた。
さっきの、私達が目を覚ましたアラーム音は赤葦のスマホだったようで。
こっちの目覚ましは、私がいつも使っているものだ。
今から支度しないと、仕事に遅刻してしまう。
話も聞きたいけど、仕事は休めないし、どうすれば良いか分からなくなって。
焦りを表現するように手をバタバタと動かしていた。
それを見ていた赤葦が、吹き出すように笑って目覚ましを止める。
「続きは、帰ってきてから話しましょう。顔を洗って、化粧して、仕事に行って下さい。」
慌てている私でも、ちゃんと聞き取れるように一言ずつ区切った指示が聞こえた。
今の、りらを神格化しているのが間違いじゃないのなら。
赤葦の私に対する気持ちは、多分ホンモノじゃない。
神様の傍に居られる手段として、私を好きになろうとするんだ。
「きとりさん、失礼な事を考えてませんか。」
「…え?何が?」
確かに人の気持ちを疑うなんて、失礼な事だけど。
それを読まれるとは思わなかった。
盛大な溜め息を吐いてから、私を真剣に見詰める眼が怖い。
「…俺、正直に言うと。昔は貴女と付き合えば、恋人から結婚まで持っていければ、りらの傍に居られると、思ってました。」
今は違うと、理由まで含めて話してくれようとしている。
こういう、面倒なのは嫌いな筈なのに、理解が追い付かない私の為に。
それなら、私も真剣に受け止めてやらないといけない。
息を飲んで、次の言葉を待とうとした時…。
目覚まし時計が、音を立てた。
さっきの、私達が目を覚ましたアラーム音は赤葦のスマホだったようで。
こっちの目覚ましは、私がいつも使っているものだ。
今から支度しないと、仕事に遅刻してしまう。
話も聞きたいけど、仕事は休めないし、どうすれば良いか分からなくなって。
焦りを表現するように手をバタバタと動かしていた。
それを見ていた赤葦が、吹き出すように笑って目覚ましを止める。
「続きは、帰ってきてから話しましょう。顔を洗って、化粧して、仕事に行って下さい。」
慌てている私でも、ちゃんと聞き取れるように一言ずつ区切った指示が聞こえた。
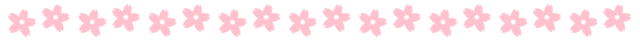
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする