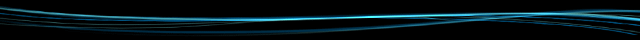
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
ラ・カンパネラ【PSYCHO-PASS】
第35章 過去編:名前のない怪物
槙島を一瞥する藤間に返答するように、槙島は小さく肩をすくめた。
「そうして聖護くんは僕に不思議な薬をくれたんだ。人体を標本化する不思議な薬をね。」
混乱する瞳子には、すでに藤間の言葉は届かない。嗚咽にうつむく後頭部を上滑りして行くだけだった。
「それで?これから君はどうするつもりなんだい?」
「また、ここ扇島で僕らにふさわしい城を見つけて、そこで暮らすよ。一時は、扇島なんてこのまま無くなっても良いとすら思ったけど、彼女に再会して考えが変わった。」
「生贄に橋田とアルトロマージを選んだのは正解だった。成り行き上とは言え、彼らがいなくなれば他に廃棄区画解体運動を牽引する人物はいない。きっと昔のような扇島が蘇るさ。」
藤間は再びアルトロマージの肉にボールペンを突き立てて、満足げに微笑んだ。
扇島製鉄所周辺の捜査は混迷を極めた。
正確なマップなど存在しない場所で、一係の刑事たちは現在地と過去の図面を照らし合わせながら、聞き込みで得た情報だけを頼りに、一人の男を捜していた。
センバ――長きにわたり、ここ扇島の顔役を務めていた男だ。現在は隠居しこの製鉄所のどこかで隠居生活を送っていると言う。
だが大した情報も得られず、捜査員達の疲労も激しかったので泉と慎也は宜野座達に先に戻るように促した。
「――まるで雲を掴むような捜査だな。」
「えぇ。このままじゃ消耗戦になるわね。」
ハァと息を吐けば、寒さで白い息が上がる。
それを見た慎也は、泉に自分のマフラーを巻いてやる。
「お前も戻ってるか?後は俺達でやる。」
「何言ってるのよ。霜村監視官に啖呵切ったのは私よ。手ぶらじゃ帰れないわ。」
「お待たせ~。冷めないうちに食えよ。扇島特製、何が入ってるか分からない肉まん。」
紙袋を抱えて戻って来た佐々山は、二人に肉まんを差し出す。
「有難う、佐々山くん。」
泉はそれを受け取れば、迷っている慎也を尻目にがぶりとかぶりついた。
「おい、泉――。」
「美味しいわよ。食べたら?」
「ははっ。さすが日向チャン。」
二人に促されて、慎也も恐る恐る肉まんにかぶりつく。
「――美味い。」
「だろ?こ~ゆ~とこの食い物が美味いのは一般人時代に検証済みだ。」
佐々山はそう言いながら一気に肉まんを食べれば今日の成果を報告する。
「そうして聖護くんは僕に不思議な薬をくれたんだ。人体を標本化する不思議な薬をね。」
混乱する瞳子には、すでに藤間の言葉は届かない。嗚咽にうつむく後頭部を上滑りして行くだけだった。
「それで?これから君はどうするつもりなんだい?」
「また、ここ扇島で僕らにふさわしい城を見つけて、そこで暮らすよ。一時は、扇島なんてこのまま無くなっても良いとすら思ったけど、彼女に再会して考えが変わった。」
「生贄に橋田とアルトロマージを選んだのは正解だった。成り行き上とは言え、彼らがいなくなれば他に廃棄区画解体運動を牽引する人物はいない。きっと昔のような扇島が蘇るさ。」
藤間は再びアルトロマージの肉にボールペンを突き立てて、満足げに微笑んだ。
扇島製鉄所周辺の捜査は混迷を極めた。
正確なマップなど存在しない場所で、一係の刑事たちは現在地と過去の図面を照らし合わせながら、聞き込みで得た情報だけを頼りに、一人の男を捜していた。
センバ――長きにわたり、ここ扇島の顔役を務めていた男だ。現在は隠居しこの製鉄所のどこかで隠居生活を送っていると言う。
だが大した情報も得られず、捜査員達の疲労も激しかったので泉と慎也は宜野座達に先に戻るように促した。
「――まるで雲を掴むような捜査だな。」
「えぇ。このままじゃ消耗戦になるわね。」
ハァと息を吐けば、寒さで白い息が上がる。
それを見た慎也は、泉に自分のマフラーを巻いてやる。
「お前も戻ってるか?後は俺達でやる。」
「何言ってるのよ。霜村監視官に啖呵切ったのは私よ。手ぶらじゃ帰れないわ。」
「お待たせ~。冷めないうちに食えよ。扇島特製、何が入ってるか分からない肉まん。」
紙袋を抱えて戻って来た佐々山は、二人に肉まんを差し出す。
「有難う、佐々山くん。」
泉はそれを受け取れば、迷っている慎也を尻目にがぶりとかぶりついた。
「おい、泉――。」
「美味しいわよ。食べたら?」
「ははっ。さすが日向チャン。」
二人に促されて、慎也も恐る恐る肉まんにかぶりつく。
「――美味い。」
「だろ?こ~ゆ~とこの食い物が美味いのは一般人時代に検証済みだ。」
佐々山はそう言いながら一気に肉まんを食べれば今日の成果を報告する。
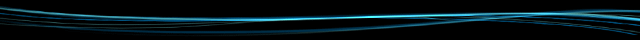
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする