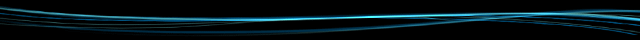
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
ラ・カンパネラ【PSYCHO-PASS】
第35章 過去編:名前のない怪物
「俺は、女好きが高じて潜在犯落ちした男だぞ。」
これが、執行官佐々山光留の口癖だった。
「あっれ~?日向チャン!それに青柳監視官サマ!二人して美女が何してんの?」
休憩なのだろう。佐々山がいつもの通り軽いノリで近付いて来るものだから、泉と青柳は目を合わせて苦笑した。
「サボリ。たまにはね。仲間に入る?」
「お、良いの?是非是非。」
そう言えば、佐々山を連れて泉は喫煙室に入って行った。
「一本頂戴?」
「ん。てか日向チャン、禁煙してなかった?」
「内緒よ。バレたらうるさいんだから。」
「あぁ、狡噛くん?意外ね。そう言うの気にしなさそうなのに。」
泉の口から出て行く紫煙を見ながら、青柳は苦笑した。
「そうでもないわよ?意外と神経質なの。シャツにアイロン掛けてないと怒るし。」
「アイツ、そんな事までさせてんのか。日向チャン、マジ狡噛なんかやめて俺にしとかな~い?」
「しとかな~い。残念ながら私はそんな慎也に心底惚れているのです。」
「へいへい、ご馳走様。」
「仲良いわよね、一係って。」
しみじみと言われて、泉と佐々山は目を合わせる。
「なんで?璃彩のところは?」
「ウチ?ホラ、お堅いのが一人いるでしょ?」
「あぁ。霜村監視官か。でもウチにもお堅いのいるわよ?」
「宜野座くんはお堅いって言っても同期だもの。どうにでもなるわ。」
その言葉に、泉は思わず笑ってしまう。
「――おっとぉ。泉、後ろ。怖い旦那が見てるケド。」
青柳の綺麗な指が後ろを指した。
泉が恐る恐る後ろを向けば、般若か!と突っ込みたくなるような表情で慎也が立っていた。
「は、ハロー?ダーリン。」
「佐々山と一緒にサボリとは良い身分だな。日向監視官。」
おちゃらける泉に、慎也は冷たく告げる。
名前で呼ばない時は、大概怒っている時だと流石の泉も分かっていた。
「ごめんって。だって書類整理ばっかりで頭痛くなったんだも~ん。」
「だもん、じゃねぇよ。青柳監視官。ウチのを引っ張りまわさないでくれ。」
「はぁ~い。ごめんなさい。狡噛くんたら相変わらず過保護ねぇ。」
そんな他愛も無い日常が尊かったのだと気付くのはそう遠くない未来なのだ。
これが、執行官佐々山光留の口癖だった。
「あっれ~?日向チャン!それに青柳監視官サマ!二人して美女が何してんの?」
休憩なのだろう。佐々山がいつもの通り軽いノリで近付いて来るものだから、泉と青柳は目を合わせて苦笑した。
「サボリ。たまにはね。仲間に入る?」
「お、良いの?是非是非。」
そう言えば、佐々山を連れて泉は喫煙室に入って行った。
「一本頂戴?」
「ん。てか日向チャン、禁煙してなかった?」
「内緒よ。バレたらうるさいんだから。」
「あぁ、狡噛くん?意外ね。そう言うの気にしなさそうなのに。」
泉の口から出て行く紫煙を見ながら、青柳は苦笑した。
「そうでもないわよ?意外と神経質なの。シャツにアイロン掛けてないと怒るし。」
「アイツ、そんな事までさせてんのか。日向チャン、マジ狡噛なんかやめて俺にしとかな~い?」
「しとかな~い。残念ながら私はそんな慎也に心底惚れているのです。」
「へいへい、ご馳走様。」
「仲良いわよね、一係って。」
しみじみと言われて、泉と佐々山は目を合わせる。
「なんで?璃彩のところは?」
「ウチ?ホラ、お堅いのが一人いるでしょ?」
「あぁ。霜村監視官か。でもウチにもお堅いのいるわよ?」
「宜野座くんはお堅いって言っても同期だもの。どうにでもなるわ。」
その言葉に、泉は思わず笑ってしまう。
「――おっとぉ。泉、後ろ。怖い旦那が見てるケド。」
青柳の綺麗な指が後ろを指した。
泉が恐る恐る後ろを向けば、般若か!と突っ込みたくなるような表情で慎也が立っていた。
「は、ハロー?ダーリン。」
「佐々山と一緒にサボリとは良い身分だな。日向監視官。」
おちゃらける泉に、慎也は冷たく告げる。
名前で呼ばない時は、大概怒っている時だと流石の泉も分かっていた。
「ごめんって。だって書類整理ばっかりで頭痛くなったんだも~ん。」
「だもん、じゃねぇよ。青柳監視官。ウチのを引っ張りまわさないでくれ。」
「はぁ~い。ごめんなさい。狡噛くんたら相変わらず過保護ねぇ。」
そんな他愛も無い日常が尊かったのだと気付くのはそう遠くない未来なのだ。
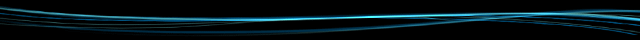
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする