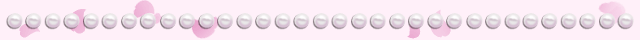
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
シンデレラと白雪姫
第3章 Concentration
「雪、入るよ」
ノックはすれど返事はなく、シンデレラはスイートポテトとラッシーを持って部屋に入った。
白雪姫はというと、真っ暗な部屋でベッドにダイブしたまま微動だにしなかった。
が、食べ物の匂いを嗅ぎつけてがばっと起き上がる。
「あんたがお世話になったお城の人たちがどうかなる前に国を助けに行かなあかんやろ?ほら、食べて元気出しや!あんたが居れへんかったらこんな無茶できひん。せやからやってみよや?」
この二人、実は同い年らしいが胃袋を掴んだ側と掴まれた側でパワーバランスが構築されてしまったらしく、白雪姫の威勢は激減していた。
「…せや言うてもうちは…『ああもうええ加減にしぃや!!!』」
うじうじしていても何も進まない。
「頼む、一生のお願いや。父さんを助けるために力を貸して下さい。」
三つ指をつくシンデレラの手を見て白雪姫は絶句した。あかぎれの目立つ乾燥した手。ところどころ霜焼けや切り傷のある長い指…それに対して自分の手はただ白い。乾燥とは無縁な白雪姫にとっては自分の甘さを突きつけられたも同然だった。
突然すっくと立ち上がってガサゴソしていたかと思うと、シンデレラを抱き起こし、その手を取った。
「こんくらいはさせて。」そう言って苦労を重ねてきたその手にハンドクリームを塗り込んだ。
そして当日、2人はドレスに身を包み、城内へと潜り込んでいた。着飾った京都国の国中の年頃の娘が集結していた。そしてクリスマスダンスパーティーということで同じく、貴族の子息も多く集まっていた。
ガヤガヤとうるさかったダンスホールが突然静かになった。女王、大臣、王子のお出ましである。
女王の挨拶の後はゆったりと音楽が流れ始め、お目当ての娘を誘う飢えた獣や、玉の輿を狙うケダモノの宴が始まった。
王子は早くも多くのケダモノに囲まれていたが彼女たちには見向きもせず、立食に没頭していた。
よく食べるなぁ…とシンデレラが眺めているとふと王子と目が合い、反射で逸らした。
「雪…しばらくしたら抜け出そう?そこで小人たちと合流。もしかしたらお城の人たちから何か聞けるかもしれない。運次第では大臣か女王に接触できるかも!」
二人は固く頷いた。
「よろしければ一曲ご一緒願えませんか?」
八ッ橋を食べていたシンデレラは耳を疑った。
そして他人事だと思って無視することにした。
ノックはすれど返事はなく、シンデレラはスイートポテトとラッシーを持って部屋に入った。
白雪姫はというと、真っ暗な部屋でベッドにダイブしたまま微動だにしなかった。
が、食べ物の匂いを嗅ぎつけてがばっと起き上がる。
「あんたがお世話になったお城の人たちがどうかなる前に国を助けに行かなあかんやろ?ほら、食べて元気出しや!あんたが居れへんかったらこんな無茶できひん。せやからやってみよや?」
この二人、実は同い年らしいが胃袋を掴んだ側と掴まれた側でパワーバランスが構築されてしまったらしく、白雪姫の威勢は激減していた。
「…せや言うてもうちは…『ああもうええ加減にしぃや!!!』」
うじうじしていても何も進まない。
「頼む、一生のお願いや。父さんを助けるために力を貸して下さい。」
三つ指をつくシンデレラの手を見て白雪姫は絶句した。あかぎれの目立つ乾燥した手。ところどころ霜焼けや切り傷のある長い指…それに対して自分の手はただ白い。乾燥とは無縁な白雪姫にとっては自分の甘さを突きつけられたも同然だった。
突然すっくと立ち上がってガサゴソしていたかと思うと、シンデレラを抱き起こし、その手を取った。
「こんくらいはさせて。」そう言って苦労を重ねてきたその手にハンドクリームを塗り込んだ。
そして当日、2人はドレスに身を包み、城内へと潜り込んでいた。着飾った京都国の国中の年頃の娘が集結していた。そしてクリスマスダンスパーティーということで同じく、貴族の子息も多く集まっていた。
ガヤガヤとうるさかったダンスホールが突然静かになった。女王、大臣、王子のお出ましである。
女王の挨拶の後はゆったりと音楽が流れ始め、お目当ての娘を誘う飢えた獣や、玉の輿を狙うケダモノの宴が始まった。
王子は早くも多くのケダモノに囲まれていたが彼女たちには見向きもせず、立食に没頭していた。
よく食べるなぁ…とシンデレラが眺めているとふと王子と目が合い、反射で逸らした。
「雪…しばらくしたら抜け出そう?そこで小人たちと合流。もしかしたらお城の人たちから何か聞けるかもしれない。運次第では大臣か女王に接触できるかも!」
二人は固く頷いた。
「よろしければ一曲ご一緒願えませんか?」
八ッ橋を食べていたシンデレラは耳を疑った。
そして他人事だと思って無視することにした。
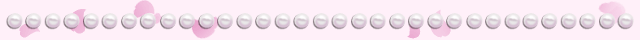
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする