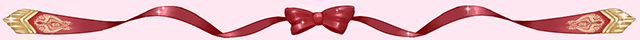
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
たまのケージ【ヒロアカ】
第14章 可哀想な2人(相澤消太)
それは、ある日曜日の昼下がりの出来事だった。
「消太、私と別れて欲しいの」
相澤消太、30歳。
突然3年付き合っていた彼女にフラれた。
「なんかね、付き合ってて違かったっていうか……」
なんか、違かった?
3週間とか、それ位の付き合いなら違かったと言われても納得できる。
しかし、3年も付き合っておいて違かったは流石にないだろうと消太は思った。
この3年、出来る事はやったつもりだった。
うっすらと、彼女との将来の事を考えたりもした。
誕生日とか、そんな節目の日には面倒だと思いつつ柄にもなくサプライズ的な事をしたりしてそれなりに彼女を喜ばせたつもりだった。
それが、違かったのだろうか。
何がいけなかった?
いや、いけなかった訳でもないのかもしれない。
「本当に、ごめんね?でも、別れたいの」
大体にして女の心なんて、秋の空のように変わりやすいものだから。
「……分かった」
消太は、ついそう答えていた。
1つの恋が終わった。
もう、次に行こうとは思えない、なかなか。
そう思っていた、この時は。
「……はぁ……」
消太は、溜息を吐きながら家に帰る為に大通りを歩いていた。
フラれた後というのは、やけに幸せそうな奴等ばかりが目についてしまう。
スマホ片手に顔を綻ばせる内定を貰ったと思しき大学生。
手なんか繋いでキャッキャと歩くカップル。
鬱陶しい。
この世のキラキラしたものが全て鬱陶しく感じてしまう。
「……はぁ……」
最早溜息しか自分の口からは出ないのだろうかと思う程、溜息が出る。
それでも歩き続けていると、爪先に何か固いものが当たった。
思わず下を見ると、そこにはスマホが1台転がっていた。
周りを見渡すと、誰もスマホの存在に気付いていないらしくどんどん通り過ぎていく。
面倒くさいもんを、見つけてしまったと消太は思った。
しかし、面倒くさい事は立て続けに起こるもんだ。
地面に転がったままのスマホが、鳴り出したのだ。
もしかしたら、持ち主が探して電話をかけているのかもしれない。
無視しようかとも思ったが、スマホは依然鳴り続けている。
仕方ない。
消太は、スマホを拾い上げると通話ボタンをタップした。
「消太、私と別れて欲しいの」
相澤消太、30歳。
突然3年付き合っていた彼女にフラれた。
「なんかね、付き合ってて違かったっていうか……」
なんか、違かった?
3週間とか、それ位の付き合いなら違かったと言われても納得できる。
しかし、3年も付き合っておいて違かったは流石にないだろうと消太は思った。
この3年、出来る事はやったつもりだった。
うっすらと、彼女との将来の事を考えたりもした。
誕生日とか、そんな節目の日には面倒だと思いつつ柄にもなくサプライズ的な事をしたりしてそれなりに彼女を喜ばせたつもりだった。
それが、違かったのだろうか。
何がいけなかった?
いや、いけなかった訳でもないのかもしれない。
「本当に、ごめんね?でも、別れたいの」
大体にして女の心なんて、秋の空のように変わりやすいものだから。
「……分かった」
消太は、ついそう答えていた。
1つの恋が終わった。
もう、次に行こうとは思えない、なかなか。
そう思っていた、この時は。
「……はぁ……」
消太は、溜息を吐きながら家に帰る為に大通りを歩いていた。
フラれた後というのは、やけに幸せそうな奴等ばかりが目についてしまう。
スマホ片手に顔を綻ばせる内定を貰ったと思しき大学生。
手なんか繋いでキャッキャと歩くカップル。
鬱陶しい。
この世のキラキラしたものが全て鬱陶しく感じてしまう。
「……はぁ……」
最早溜息しか自分の口からは出ないのだろうかと思う程、溜息が出る。
それでも歩き続けていると、爪先に何か固いものが当たった。
思わず下を見ると、そこにはスマホが1台転がっていた。
周りを見渡すと、誰もスマホの存在に気付いていないらしくどんどん通り過ぎていく。
面倒くさいもんを、見つけてしまったと消太は思った。
しかし、面倒くさい事は立て続けに起こるもんだ。
地面に転がったままのスマホが、鳴り出したのだ。
もしかしたら、持ち主が探して電話をかけているのかもしれない。
無視しようかとも思ったが、スマホは依然鳴り続けている。
仕方ない。
消太は、スマホを拾い上げると通話ボタンをタップした。
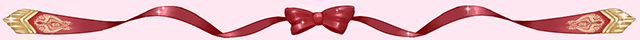
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする