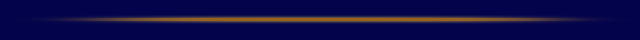
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【NARUTO】月影の恋人(R18)
第3章 奇跡の夜、口付けの朝
「おはよ」
「う、お、はよう……」
顔が近くても、抱き締めても余裕なカカシがずるい。
そりゃ、女として見てないから、かもしれないけどさ。
というか、布団は違っても、大人の男と女が隣り合って寝て、何もないなんてことがあるのだろうか。
カカシが欲情するとこなんて想像できない。
たとえ、わたしが今服を脱いでキスしても、カカシは抱いてくれない気がする。
「……カカシって、ゲイなん?」
「朝からいきなり何?
……男に欲情したことないし、フツーに女の子が好きだけど……」
いきなりの質問に、カカシが訝しげに眉を寄せた。
じゃあやっぱ、わたしに魅力がなさすぎ?
それか大事な人がいるとか……?
頭に浮かんだ言葉にズキンと心が痛んだ。
「じゃあ、なんであたしのこと抱かへんの?」
答えなんて聞きたくないのに、言葉が口からこぼれ落ちた。
「んー……、オレ、先生やってたって言ったでしょ?
その教え子の1人が、夕月と同い年くらいの女の子だから、かも。
その子がこんな好きでもないおじさんに抱かれるのなんて、想像したくないからね」
「私はその子とはちゃう!!」
予想以上に大きな声が出た。
女として見てもらえないことか、抱いてもらえないことか、子供扱いされたことか、何が悲しいのかもうよく分からないけど、とにかく悲しかった。
「それは、そうだけど……。ちょ、夕月、どうしたの?」
カカシが戸惑っている。
そりゃそうだ。
さっきまで笑ってたのに、変な質問をして勝手に怒って。
まるっきり子供な自分がすごく嫌だ……。
でも、もう自分の中に溢れかえっている気持ちを誤魔化せなかった。
「わたしは、カカシが……、好き……」
想いの大きさとは裏腹に消え入りそうな情けない声だった。
「え……?」
カカシが呆然とわたしを見る。
「わたしは!カカシが好きやの!!!
分かったら、もう帰って!!!」
答えは分かりきってて聞きたくなかったから、グイグイとカカシの体を出口の方に押す。
「え!?ちょっ!なんで告白しといて追い出すの!!」
「だって!答えなんてわかってるし聞きたくないもん!!」
カカシの顔も見れずにぎゅーぎゅー押していると、ぐっと手首を掴まれて近くの壁に押さえつけられる。
「ゴメン……」
「う、お、はよう……」
顔が近くても、抱き締めても余裕なカカシがずるい。
そりゃ、女として見てないから、かもしれないけどさ。
というか、布団は違っても、大人の男と女が隣り合って寝て、何もないなんてことがあるのだろうか。
カカシが欲情するとこなんて想像できない。
たとえ、わたしが今服を脱いでキスしても、カカシは抱いてくれない気がする。
「……カカシって、ゲイなん?」
「朝からいきなり何?
……男に欲情したことないし、フツーに女の子が好きだけど……」
いきなりの質問に、カカシが訝しげに眉を寄せた。
じゃあやっぱ、わたしに魅力がなさすぎ?
それか大事な人がいるとか……?
頭に浮かんだ言葉にズキンと心が痛んだ。
「じゃあ、なんであたしのこと抱かへんの?」
答えなんて聞きたくないのに、言葉が口からこぼれ落ちた。
「んー……、オレ、先生やってたって言ったでしょ?
その教え子の1人が、夕月と同い年くらいの女の子だから、かも。
その子がこんな好きでもないおじさんに抱かれるのなんて、想像したくないからね」
「私はその子とはちゃう!!」
予想以上に大きな声が出た。
女として見てもらえないことか、抱いてもらえないことか、子供扱いされたことか、何が悲しいのかもうよく分からないけど、とにかく悲しかった。
「それは、そうだけど……。ちょ、夕月、どうしたの?」
カカシが戸惑っている。
そりゃそうだ。
さっきまで笑ってたのに、変な質問をして勝手に怒って。
まるっきり子供な自分がすごく嫌だ……。
でも、もう自分の中に溢れかえっている気持ちを誤魔化せなかった。
「わたしは、カカシが……、好き……」
想いの大きさとは裏腹に消え入りそうな情けない声だった。
「え……?」
カカシが呆然とわたしを見る。
「わたしは!カカシが好きやの!!!
分かったら、もう帰って!!!」
答えは分かりきってて聞きたくなかったから、グイグイとカカシの体を出口の方に押す。
「え!?ちょっ!なんで告白しといて追い出すの!!」
「だって!答えなんてわかってるし聞きたくないもん!!」
カカシの顔も見れずにぎゅーぎゅー押していると、ぐっと手首を掴まれて近くの壁に押さえつけられる。
「ゴメン……」
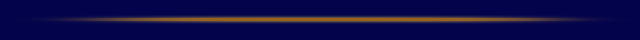
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする