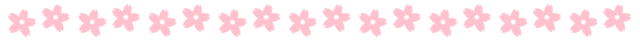
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
きみを想う
第13章 夏夜の願い
季節は移ろい、夜でも空気は熱を孕み額に汗が浮かぶ。
「ただいまー」
いつもならすぐに駆けてくるすずらんが、今日は来ない。
それどころか返事もない。
今は夜の10時。
出かけるには遅すぎる時間だ。
不思議に思いリビングに行くと、エプロンをつけたまま、すずらんがキッチンのテーブルに顔を預けて寝ている。
テーブルには新しい家の設計図と、壁紙などのカタログが広げられている。
すやすやと気持ち良さそうに寝ているから、起こすこともないかとこのままベッドに連れていこうと抱き抱えると、すずらんが目を開ける。
「ん…、カカシ?」
「ただいま」
手を枕みたいに頬の下に引いていたから、顔にはその跡がくっきりとついてしまっている。
そのあとをそっと撫でると、トロンとした顔ですずらんがオレを見上げ、そして慌てた顔で急速に覚醒していく。
「あっごめん。
カタログ見てたら寝ちゃったみたい…。
お疲れ様!
すぐご飯にするね」
「自分でできるから大丈夫だよ。
すずらんはもう寝たら?
なんか疲れた顔してる」
すずらんを下ろし、おでこに手を当てる。
いつもより少し温かい気もするが、熱というほどでもなさそうだ。
「そう、かな?
なんか最近ちょっとダルいんだよね。すぐ眠くなっちゃうし。
夏バテかなぁ…。
でもあとおそば茹でるだけだし大丈夫!」
「ほんと?」
「うん!」
気になるが、熱もないしすずらんの言う通り、最近暑い日が続いてるから夏バテかもしれない。
「体調悪いの続くなら病院行きなよ?」
「うん。わかった」
ご飯の支度を手伝って、2人で食卓につく。
蕎麦のつけ汁にはナスやネギ、豚肉がたくさん入っていてすごく美味しそうだ。
「ん、うま…」
一口食べて呟くと、「でしょ」とすずらんが嬉しそうに微笑む。
ああ。可愛い。
この笑顔にオレは何度絆されているんだろう。
蕎麦を食べ終わり茶を飲みながら、今日見たチラシのことを思い出す。
「あ、そうだ。
今年もまた花火あるみたいだよ」
去年すずらんと一緒に見た花火。
その日、2人は初めて手を繋ぎ、キスをした。
来年も同じ場所で見ようと約束した、あの思い出の花火。
「行きたい!
あれからもう一年なんだねぇ」
すずらんが食器を片付けながらしみじみ言う。
「ただいまー」
いつもならすぐに駆けてくるすずらんが、今日は来ない。
それどころか返事もない。
今は夜の10時。
出かけるには遅すぎる時間だ。
不思議に思いリビングに行くと、エプロンをつけたまま、すずらんがキッチンのテーブルに顔を預けて寝ている。
テーブルには新しい家の設計図と、壁紙などのカタログが広げられている。
すやすやと気持ち良さそうに寝ているから、起こすこともないかとこのままベッドに連れていこうと抱き抱えると、すずらんが目を開ける。
「ん…、カカシ?」
「ただいま」
手を枕みたいに頬の下に引いていたから、顔にはその跡がくっきりとついてしまっている。
そのあとをそっと撫でると、トロンとした顔ですずらんがオレを見上げ、そして慌てた顔で急速に覚醒していく。
「あっごめん。
カタログ見てたら寝ちゃったみたい…。
お疲れ様!
すぐご飯にするね」
「自分でできるから大丈夫だよ。
すずらんはもう寝たら?
なんか疲れた顔してる」
すずらんを下ろし、おでこに手を当てる。
いつもより少し温かい気もするが、熱というほどでもなさそうだ。
「そう、かな?
なんか最近ちょっとダルいんだよね。すぐ眠くなっちゃうし。
夏バテかなぁ…。
でもあとおそば茹でるだけだし大丈夫!」
「ほんと?」
「うん!」
気になるが、熱もないしすずらんの言う通り、最近暑い日が続いてるから夏バテかもしれない。
「体調悪いの続くなら病院行きなよ?」
「うん。わかった」
ご飯の支度を手伝って、2人で食卓につく。
蕎麦のつけ汁にはナスやネギ、豚肉がたくさん入っていてすごく美味しそうだ。
「ん、うま…」
一口食べて呟くと、「でしょ」とすずらんが嬉しそうに微笑む。
ああ。可愛い。
この笑顔にオレは何度絆されているんだろう。
蕎麦を食べ終わり茶を飲みながら、今日見たチラシのことを思い出す。
「あ、そうだ。
今年もまた花火あるみたいだよ」
去年すずらんと一緒に見た花火。
その日、2人は初めて手を繋ぎ、キスをした。
来年も同じ場所で見ようと約束した、あの思い出の花火。
「行きたい!
あれからもう一年なんだねぇ」
すずらんが食器を片付けながらしみじみ言う。
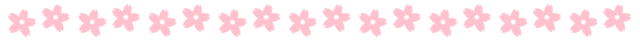
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする