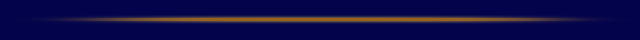
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
在りし日の歌【文スト】【短編集】
第1章 招かれざる客
時は進み定時になった頃、皆がいそいそと帰宅の準備をする中に二人の姿があった。
「…という訳だから。分かったかな?敦君。」
「分かりたくもありませんよ!帰宅する後をつけるなんて、下手したらストーカーで訴えられますからね?」
「では君は愛理ちゃんの家が何処なのか気にならないのかい?」
悪戯っ子みたくニヤニヤする彼は返ってくる答えが分かっていてわざと聞いているとしか思えない。
「いやっ、それは気になります、けど…」
「だろう?分かったなら着いて来給え!」
丁度その時、帰りの挨拶を済ませ事務所の扉を開けた彼女。
其れから少し間を置いて太宰と敦も扉を開ける。
……が、既に彼女の気配は忽然と消えていた。
「やっぱり異能力使ってますね…。どうするんですか?これじゃ跡つけられませんよ!?」
やる気満々になっている彼の様子に満足した太宰は懐から或る物を取り出す。
「ふっふっふっ。此れを見給え!敦君!」
「こっ、此れは…!!」
その反応を待っていました。と云わんばかりの太宰が持っていたのは携帯電話だった。
「……って、只の携帯電話じゃないですか。電話でもして本人に聞く心算ですか?」
「よーく見給えよ。」
「真逆とは思いますがGPSですか?」
「そうだよー。先刻外套の襟首の裏に付けたんだ。此れさえ有れば愛理ちゃんが何処で何をしていても私が駆けつけられるのだよ!ふふふっ。」
「…あ、もしもし?警察ですか?今ストーカーの現行犯が横に居るんですけど…。」
敦の携帯を凄まじい勢いでもぎ取ると通話終了釦を押して何事も無かったかの様に持ち主に返す。
そして漸くGPSを頼りに彼女が居るであろう方向へと歩き出す。
「というか何をしているか迄は流石に分かりませんし、そもそも外套変えたり夏になったりしたら如何するんですか。」
「簡単だよ。また付ければいいのさ!」
敦はこの如何しようもないストーカー自殺嗜癖に人生を救われたのだと思うと急にやるせ無い気持ちに襲われた。
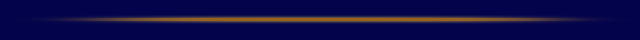
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする