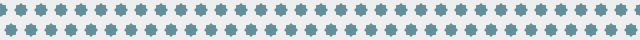
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
息子の親友
第1章 息子の親友
どうしてこんなにこんなに胸が騒ぐのだろうか…大人の男ではあるが少年の危うさもある。
息子達は笑いながら、我が家にやって来た。
「こんにちは、ユンスさん」
彼はいつもみたいに挨拶をしてくれた。
低めの声が何とも言えないくらいセクシーで耳が擽ったい。
「こんにちは」
私は少しはにかんで彼に挨拶をした、握手を交わすときドキドキした。
彼は悪戯っ子の様に笑っている。
心臓の音聞こえてないかしら…頬は赤くなっていないかしら…そんなことを考えていた。
「母さん、ウォンシクと勉強するから部屋には入って来ないで」
それだけ云うと、彼等は部屋に鍵を掛けて中に篭ってしまった。
相変わらず息子のホンビンは素っ気ない。思春期になってから余計にだ。
部屋に入って1時間も立つとゲーム音や笑い声が聞こえ始める。
勉強するんじやなかったの?と呆れてしまう。
「まるで子供ね」と呟いて、彼らの為にホットココアとシフォンケーキを作り準備していた。
鼻歌を歌いながら、何気なく振り返ると、ウォンシクが微笑んで立っていた。
私は思わず驚いて、手にしていたシフォンケーキのお皿を落としそうになった。
「びっくりした」
「すいません、驚かしたしまって」
「声掛けてくれたらよかったのに…」
「あんまり楽しそうにされてたんで声を掛けずらくて…」
「どうしたの?」
「喉が渇いてしまって…すいませんが何か飲み物をいただけませんか?」
「ああ、それなら今持っていこうとしてたのよ」
#ユンス#は笑顔で答える。
「お菓子作りが好きなんですか?」
「ええ…まあね…ホンビンが小さい頃はよく作ったの。けど今はこうして友達が遊びに来た時ぐらいしか作らなくなったし、彼も食べなくなったわ」
「へえ、そうなんですか」
「子ども扱いしてほしく無いんじゃないのかしらね…」
#ユンス#は笑うと、ウォンシクがぽつりと「うらやましいな」と云った。
「え?何が?」
「羨ましいといったんですよ。こんなに愛情を注がれているホンビンが羨ましいって」
「ええ?」
「僕もあなたのような女性に愛情を注いでもらいたかったな…」
そういって彼は私が手にしていたシフォンケーキをパクリと嚙り付いた。
シフォンケーキの生クリームが口の端についている。
息子達は笑いながら、我が家にやって来た。
「こんにちは、ユンスさん」
彼はいつもみたいに挨拶をしてくれた。
低めの声が何とも言えないくらいセクシーで耳が擽ったい。
「こんにちは」
私は少しはにかんで彼に挨拶をした、握手を交わすときドキドキした。
彼は悪戯っ子の様に笑っている。
心臓の音聞こえてないかしら…頬は赤くなっていないかしら…そんなことを考えていた。
「母さん、ウォンシクと勉強するから部屋には入って来ないで」
それだけ云うと、彼等は部屋に鍵を掛けて中に篭ってしまった。
相変わらず息子のホンビンは素っ気ない。思春期になってから余計にだ。
部屋に入って1時間も立つとゲーム音や笑い声が聞こえ始める。
勉強するんじやなかったの?と呆れてしまう。
「まるで子供ね」と呟いて、彼らの為にホットココアとシフォンケーキを作り準備していた。
鼻歌を歌いながら、何気なく振り返ると、ウォンシクが微笑んで立っていた。
私は思わず驚いて、手にしていたシフォンケーキのお皿を落としそうになった。
「びっくりした」
「すいません、驚かしたしまって」
「声掛けてくれたらよかったのに…」
「あんまり楽しそうにされてたんで声を掛けずらくて…」
「どうしたの?」
「喉が渇いてしまって…すいませんが何か飲み物をいただけませんか?」
「ああ、それなら今持っていこうとしてたのよ」
#ユンス#は笑顔で答える。
「お菓子作りが好きなんですか?」
「ええ…まあね…ホンビンが小さい頃はよく作ったの。けど今はこうして友達が遊びに来た時ぐらいしか作らなくなったし、彼も食べなくなったわ」
「へえ、そうなんですか」
「子ども扱いしてほしく無いんじゃないのかしらね…」
#ユンス#は笑うと、ウォンシクがぽつりと「うらやましいな」と云った。
「え?何が?」
「羨ましいといったんですよ。こんなに愛情を注がれているホンビンが羨ましいって」
「ええ?」
「僕もあなたのような女性に愛情を注いでもらいたかったな…」
そういって彼は私が手にしていたシフォンケーキをパクリと嚙り付いた。
シフォンケーキの生クリームが口の端についている。
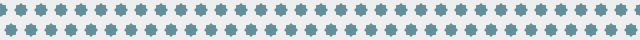
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする