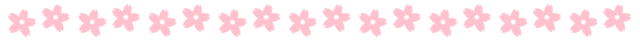
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【HQ】繋がる縁の円
第13章 お食事会
皆の視線が痛いくらい私に向いてて、それから逃げるように下を向く。
本格的に、どうすれば良いのか分からない。
「りら、いい加減にしなさい。」
父が苛々しているのが、声だけで分かる。
萎縮してしまって、更に言葉が出なくなった。
膝に乗せていた手が震える。
それを止めるように、隣から伸びてきた手が重ねられた。
「りら、ごめんな。お前が、あぁ言ってくれたから、紹介され待ちしてだが。やっぱ、俺から挨拶させて?」
私にだけ聞こえるような小さな声。
私を庇おうとしてくれているのが分かって、手を握り返した。
「私が、言う。」
庇われて、護られて。
代わりにやって貰ってばかりじゃいけない。
自分で、秋紀を家族に紹介したいと思ったんだ。
それすら、実行出来なくてどうする。
「秋紀さんとは、数ヶ月前からお付き合いしてます。まだ未熟者ではありますが、見守って頂けますようお願い致します。」
顔を上げて、はっきりと声に出すと、何故か空気が固まった。
「…姉ちゃーん。それじゃ結婚の挨拶に来た台詞だよ。しかも、相手側の両親に言うようなやつ。」
その理由は、妹の突っ込みによって判明。
「そうなの。」
「そうとしか、聞こえない。」
「じゃあ、アンタはどうやって紹介したの。」
どこが変なのかは分からないし、例文でも出してくれとばかりに妹の方を向いた。
「京治が元々家族と知り合いだからさ。付き合ってます、以上。」
「適当すぎる。」
「重苦しい、真面目な挨拶してどうすんのよ。結婚はしないのに。」
私と妹が会話を始めると、8割方は言い合いになる。
今回も、そうなる気配がしてきたけど。
「…今はまだ、ね。」
赤葦さんに口を挟まれて止まった。
本格的に、どうすれば良いのか分からない。
「りら、いい加減にしなさい。」
父が苛々しているのが、声だけで分かる。
萎縮してしまって、更に言葉が出なくなった。
膝に乗せていた手が震える。
それを止めるように、隣から伸びてきた手が重ねられた。
「りら、ごめんな。お前が、あぁ言ってくれたから、紹介され待ちしてだが。やっぱ、俺から挨拶させて?」
私にだけ聞こえるような小さな声。
私を庇おうとしてくれているのが分かって、手を握り返した。
「私が、言う。」
庇われて、護られて。
代わりにやって貰ってばかりじゃいけない。
自分で、秋紀を家族に紹介したいと思ったんだ。
それすら、実行出来なくてどうする。
「秋紀さんとは、数ヶ月前からお付き合いしてます。まだ未熟者ではありますが、見守って頂けますようお願い致します。」
顔を上げて、はっきりと声に出すと、何故か空気が固まった。
「…姉ちゃーん。それじゃ結婚の挨拶に来た台詞だよ。しかも、相手側の両親に言うようなやつ。」
その理由は、妹の突っ込みによって判明。
「そうなの。」
「そうとしか、聞こえない。」
「じゃあ、アンタはどうやって紹介したの。」
どこが変なのかは分からないし、例文でも出してくれとばかりに妹の方を向いた。
「京治が元々家族と知り合いだからさ。付き合ってます、以上。」
「適当すぎる。」
「重苦しい、真面目な挨拶してどうすんのよ。結婚はしないのに。」
私と妹が会話を始めると、8割方は言い合いになる。
今回も、そうなる気配がしてきたけど。
「…今はまだ、ね。」
赤葦さんに口を挟まれて止まった。
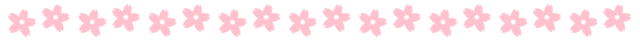
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする