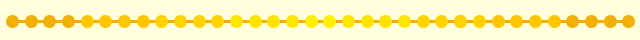
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
この日々を謳歌せよ【おそ松さん】
第6章 姉妹
「いや、何で、え…?!」
「あー落ち着いてカラ松。違うから」
今日はいろいろ衝撃的なことがありすぎて彼の頭はぐちゃぐちゃらしい。
遂にはショートしたように唐突にベッドにバタンキューしてしまった。
本気ではなかったとはいえ流石にヤバかったか。
顔をベッドに沈めるカラ松のそばにしゃがみ、頭をぽんぽんと撫でる。
ごめんね、弄りすぎた。
そう言うと彼はちらりと瞳に私を映した。
「でも流石にカラ松みたいな成人男性を独り暮らしの私の家に泊めるっていうのもさ、ちょっとアレだったから」
「…普通のホテルではダメだったのか」
成る程カラ松の言葉は正論だ。
ホテルはホテルだが、ここは単なるお泊まり用ではない。
独り暮らしの女性の元に成人男性を泊めるのはどうたらとか言う私が連れて来る場所ではなかった。
「……他のホテルが、もう一杯になってて」
「そうなのか?この町そんなに人いたんだな」
「……」
「ん?待て、。お前いつ予約なんてとったんだ?」
「うっ」
苦し紛れに答える私の言葉に最初納得したカラ松だったが、すぐにその違和感に気付く。
なんでこんな時だけ鋭いの。
「確か病院でも俺にずっと付き添っていてくれてたはずじゃ…」
あー、もうダメだ。
白状するしかないことを悟った。
「、お前はなぜ」
「あぁもう、言えばいいんでしょ言えば!全部あの男のせいだってね!!」
「……男?」
「イヤミさん!!」
そう、時は病院でカラ松がトイレに行っていた一瞬に遡る。
『、あの次男はこの後どうするザンスか?』
『放っておけないし、今日は家に泊めようかなって』
『泊める?!?!そんなこと許されて良いはずがないザンス!ミーに任せてちょ、素敵なホテルを予約してあげるザンス!』
『耳元で叫ばないでくださいよ…』
『この住所のとこに行くザンスよ、ここから近いし、チミにもきっと気に入ってもらえるザンス』
『……はぁ、どうもありがとうございます』
今考えればおかしいのだ。
泊めるのは許されないとか言いながらちゃっかり私の分も予約してあげたザンスなんて。
ミーのおごりなんて感謝してちょ!と何度も繰り返して去っていった彼に、もし叶うのなら力の限り拳をぶつけたい。
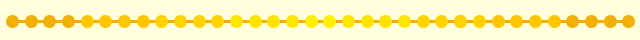
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする