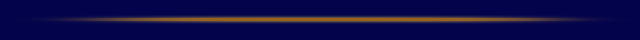
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
儚さゆえの愛しさで【銀魂】
第4章 "雪螢"
千里side
「この後に雪女は寿命がきて、この剣に自分の思いを託したと言います。」
「む、いきなりまとめに入ったな。」
桂が訝しげに千里は見るが、話す気は一切ないのでそっぽを向く。
ここからの話は千里にとって不快以外の何者でもない。
雪女の復讐は、成功しないからだ。
自分自身、復讐を望む立場として不吉な言葉を避けたいのもある。
しかし、どうしてもこの話は吐き気が止まらなくなり、涙が溢れるのだ。
そんな姿、宗にならまだしも桂などに見せる気はさらさら千里にはなかった。
「……まぁ、いい。」
唇を結んだまま、視線を合わそうとしていない千里を桂は見ながら呆れたように紡ぐ。
「質問はいいか?」
そして、兼ねてからの疑問を千里と宗にぶつけた。
二人は顔を見合わせた後、首をたてに降り、肯定の意を示した。
「"雨龍"とは結局何だったのだ?」
_________"雨龍"。
物語の途中に出てきた、一番謎の存在。
大人か子供か分からない、姿だけは少年の人ではない生き物。
宗はおかしそうに、口角を上げた。
桂は眉を寄せ、警戒するそぶりを見せる。
しかし、千里はその姿を珍しいと感じていた。
いや、久しぶりに見たと。
仮面を被ることのない、彼本来の笑み。
憎しみと慟哭を混ざり合わせた笑み。
「桂さん……"雨龍"なら、ここにあるんですよ。」
「……何?」
「"憎しみを糧にして生きるもの"……。それは雪女でありながら、"雪螢"と姿を変えた妖刀と同じです。」
「貴様の持っている刀がその"雨龍"だというのか?」
桂が指をさす。
宗はその柄に手をかけ、刀を抜いた。
一瞬、桂は抜刀しかけるが、思い立ったようにその手を戻した。
「妖刀、"雨龍"。」
滑らかな刃。
幾ら使っても刃は切れ味が変わることがない。
紺色の柄に包まれた美しい刀。
"雪螢"と同じ性能があるが、唯一違うところがある。
「主人には化身が見えます。」
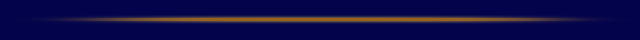
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする