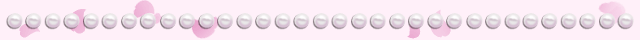
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
シンデレラと白雪姫
第2章 Believer
どれくらい走っただろうか。
黒いワンピースに腰元からの白いエプロン。母の履いていた木靴。ワンピースの上からペンダントの存在を確認して一息つく。
いつ見つかるか分からない。
でもその前にしたいことがある。
「父さん、来たよ」
街を抜けて、キャンプ場を抜けて、そのまた外れにある小屋を訪ねた。
返事がないので勝手に入る。明かりをつけて愕然とした。誰もいない。
証拠がないから仮釈放ということで世の中きら隔離されて生きていた父さんはどこへ?
「お前さんかい?シンデレラというのは」
振り返ってびっくりした。身長推定1m、斧持参の小人が私に声をかけていた。
反射で目線を合わせるべくしゃがむ。
「いかにも、私です。父のお知り合いですか?」
うむ、と頷き、小人は指笛を鳴らした。するもその更に奥の小屋から6人同じような人たちが出てくる。
「お前さんの親父は王宮直属の牢獄へ移されたさぁ。かれこれ2年になるかぇ?随分と抵抗なすったんだけどへこずって行かれた。でも儂等は信じとるよ。あの人はそんな人じゃあねえ。料理の腕の立つ人柄のいい親父さんだ。」
差し出された手を強く握る。12年間ずっと父を否定する人としか接してこれなかったシンデレラにとってこの小人たちの存在は全く新しいものだ。
「誰やそこの女」
父の使っていた小屋から女の子が出てきた。漆黒のストレートヘア。青と黄色のドッキングワンピース。赤いリボンカチューシャ。
「あのオヤジの娘か。入り、風邪ひくで」
聞けば彼女の名前は白雪姫というらしい。
「てことは前王様の王女様…」
「堅苦しいことはやめ。うちは死んだことになっててホンマはおれへんの。せやけど小人たちとあんたのお父さんが匿ってくれてたってわけ。やからあんたのオヤジさんがうちの父上を殺した罪に問われてるって聞いたときは信じられへんかった。それに今も信じてへん。やけど…王宮の方に連れて行かれたってことは話は別や。本格的に裁きが下る…何としてもそれは防がなあかん。」
シンデレラは考える。果たして白雪姫を巻き込んでいいものか。
「ええこと思いついた!」
パチンと小気味よく指が鳴る。
不敵な笑みを浮かべるシンデレラに白雪姫は内心舌を巻き、小人たちは何かよくわからないが不穏な空気を感じ取り、長老に相談するべきだと推した。
黒いワンピースに腰元からの白いエプロン。母の履いていた木靴。ワンピースの上からペンダントの存在を確認して一息つく。
いつ見つかるか分からない。
でもその前にしたいことがある。
「父さん、来たよ」
街を抜けて、キャンプ場を抜けて、そのまた外れにある小屋を訪ねた。
返事がないので勝手に入る。明かりをつけて愕然とした。誰もいない。
証拠がないから仮釈放ということで世の中きら隔離されて生きていた父さんはどこへ?
「お前さんかい?シンデレラというのは」
振り返ってびっくりした。身長推定1m、斧持参の小人が私に声をかけていた。
反射で目線を合わせるべくしゃがむ。
「いかにも、私です。父のお知り合いですか?」
うむ、と頷き、小人は指笛を鳴らした。するもその更に奥の小屋から6人同じような人たちが出てくる。
「お前さんの親父は王宮直属の牢獄へ移されたさぁ。かれこれ2年になるかぇ?随分と抵抗なすったんだけどへこずって行かれた。でも儂等は信じとるよ。あの人はそんな人じゃあねえ。料理の腕の立つ人柄のいい親父さんだ。」
差し出された手を強く握る。12年間ずっと父を否定する人としか接してこれなかったシンデレラにとってこの小人たちの存在は全く新しいものだ。
「誰やそこの女」
父の使っていた小屋から女の子が出てきた。漆黒のストレートヘア。青と黄色のドッキングワンピース。赤いリボンカチューシャ。
「あのオヤジの娘か。入り、風邪ひくで」
聞けば彼女の名前は白雪姫というらしい。
「てことは前王様の王女様…」
「堅苦しいことはやめ。うちは死んだことになっててホンマはおれへんの。せやけど小人たちとあんたのお父さんが匿ってくれてたってわけ。やからあんたのオヤジさんがうちの父上を殺した罪に問われてるって聞いたときは信じられへんかった。それに今も信じてへん。やけど…王宮の方に連れて行かれたってことは話は別や。本格的に裁きが下る…何としてもそれは防がなあかん。」
シンデレラは考える。果たして白雪姫を巻き込んでいいものか。
「ええこと思いついた!」
パチンと小気味よく指が鳴る。
不敵な笑みを浮かべるシンデレラに白雪姫は内心舌を巻き、小人たちは何かよくわからないが不穏な空気を感じ取り、長老に相談するべきだと推した。
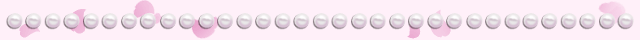
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする