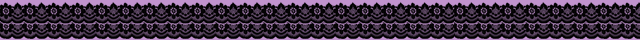
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
伏黒くんと。【呪術廻戦】
第3章 ××しないと出られない部屋 ※
二人の必死の努力も虚しく、出口はまったく見つからなかった。時計もなくどれぐらい時間が経っているかも、今が朝なのか夜なのかもわからない。空腹や口渇さえ感じなかった。
他の呪術師は助けに来てくれないのだろうか。気分だけが重たくなっていく。
「一回寝て、また目覚めたら元通りかも!」
明るい声でそう言って、鈴はベッドに横になった。
努めて明るく振る舞う彼女に倣って、伏黒もベッドに身を委ねる。
「このベッドふかふか」
「そうだな」
かなり動き回ったはずなのに疲れも眠気も襲ってこないし、鈴も同じらしい。
「本当に変な部屋ね。でも伏黒くんと一緒だからよかった」
鈴はそう笑う。いつもそんな彼女に救われる。きっと何とかなると思えるから不思議だ。
自然と唇を重ねて、抱き寄せて、ふわふわした猫っ毛を撫でる。
これぐらいのスキンシップしかしたことがなかった。
今までは。
これ以上先に進んではいけない、と思う。
だってまだ高校生で、何かあっても責任なんか取れないし、もし何かあったら負担になるのは女の方で、彼女だけは傷つけたくない。何より大事にしたい。
そんな思いとは裏腹に、下半身はすっかり疼いているのだが。
情けない、こんな状況で。
一刻も早くここから無事に出ないといけない。
「………伏黒くん、あれしたらここから出られるんだよね?」
「いや、あんなの信用するなよ」
「でも。伏黒くんとなら私、してもいいよ……?」
(イヤ、イヤ、イヤ!!!)
「いいわけないだろ!?それに本当に出れるかわからねぇ」
「だって、ここにずっといるわけにいかないでしょ?それとも私って、そんなに女として見れないの…?」
ピンク色に染まった頬と潤んだ瞳で見上げられると困る。
「そんなわけないだろ。俺だって我慢してんだよ…」
「えっ?」
言ってしまった。紛うことない本音だ。
心臓の音が、今まで聞いたことがないぐらい大きくなる。
「痛かったり、嫌だったりしたら、すぐ言えよ」
「うん…」
そう言えたのが、最後の理性だった。
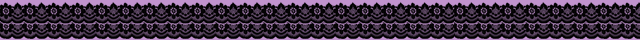
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする