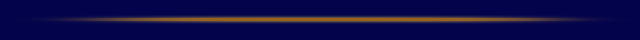
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【NARUTO】月影の恋人(R18)
第6章 痕
親父さまにいい返事を貰えないまま、ひと月が過ぎた。
でもカカシは時間が少しでもあれば会いに来てくれるし、前にも増して甘く愛してくれる。
わたしはフワフワ浮かび上がりそうなくらい幸せだった。
昼店が始まるまでの間、わたしは最近ある物に向かい合っていた。
それはハサミだ。
初めは小さなナイフでえんぴつを削ることに挑戦しようとしたが、汗と震えが止まらず断念した。
ハサミも怖いが、ナイフよりはマシだった。
震える手で紙を少しずつ切る。
呼吸が浅くならないように深呼吸したとき、無遠慮に部屋の戸が開いた。
「何やってんの?」
意地悪な目で見下ろしてくる同僚の春宵(はるよい)を睨み据える。
「なんでもいいやろ?」
プイッとそっぽを向いてまた手元に視線を落とす。
「あーあ。
火影さま可愛そう、顔に泥塗られて。
遊女なんか妻にしたら、評判ダダ下がりよね。
火影さまならいくらでも、いいとこのお嬢様が来てくれそうなのに。
なんで愛人にしとかないんだろ。
ねぇ、お荷物奥さん?」
クスクス意地悪い笑いに怒りが湧くが、唇を噛んで耐える。
いつもなら手が出ているところだが、今は親父さまの機嫌を損ねたくない。
「それだけ?
用がないならとっとと出てってや」
わたしは立ち上がり部屋から春宵を追い出すと、ピシャリと戸を閉めた。
春宵はまだ何かワーワー言っているけど、奥の間に移動して無視する。
でも本当はお荷物奥さんって言葉が、予想以上に棘になって深く刺さっていた。
ただでさえわたしは料理も裁縫もろくにできない。
その上この結婚で、わたしはカカシの顔に泥を塗ってしまうのだろうか……。
自分の幸せばかり考えて、カカシのことをまったく考えられてなかったことに今さら気づく。
わたしは迫り上がってくる涙を堪え唇を噛むと、ぎゅっと着物の裾を握りしめた。
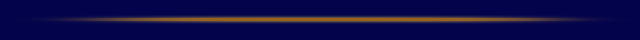
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする