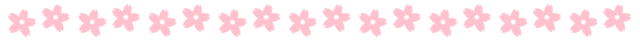
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
キメツ学園【鬼滅の刃】
第10章 果てる
階段に座り込んで話を聞いてもらうことにした。トランペットはちゃんと膝の上に置いて落ちないようにする。
「学校中の生徒がどこにいるか気配でわかってしまうんです。人間って動くでしょう。だから、気配がざわざわするんです。誰かが近づいてくると、肩を叩かれたように思ってしまって…。」
「……なるほど、それで妖精か。」
「…悲鳴嶼先輩もそんなことありますか?」
先輩は首を横に振った。
「私は違う。私は盲目で、その分他の機能が発達しているだけだ。霧雨のものはもっと特別なものだろう。」
「と、言いますと…?」
「詳しいことはわからない。だが感じるものは仕方があるまい。気配のざわめきに心を乱されぬようにするしかない。」
そう言われても、今も落ち着かない。
そこかしこで這いずり回るような、生々しい気配がうごめいているのだから。
「受け入れることだ……辛かろうが。」
「受け入れる…。」
「そのざわめきを当たり前だと思うことだ。誰になんと言われようとも。」
私はしばらく考えた。
皆に変な目で見られている気がした。気配に敏感だなんて。だって私、今どこで皆がどんな風に動いてるのかわかるんだもの。それって気持ち悪くないかな。気にしないでおこうって思っても、気になるんだもん。
カナエだって、そう。
「友達に、エスパーって疑われたんです。でもそれはしょうがないこと…なんですか。」
考えて出てきた質問が少し幼稚っぽかった。
少し恥ずかしくて縮こまっていると、悲鳴嶼先輩が答えてくれた。
「そうだ。」
私は思いっきり殴られたような、すさまじいショックを受けた。
「お前に関わる全ての事象が霧雨を作り上げている。」
そんな私をよそに先輩は話し続けた。
「それらを自ら否定するのは、悲しいことだ。」
「……?」
「疑われようとも霧雨という人間は変わらぬ。それとも、お前の友達はそれだけでお前を見放すのか。」
先輩の言っていることは難しくて。
馬鹿な私は完全に理解できなくて。
それでも。
「学校中の生徒がどこにいるか気配でわかってしまうんです。人間って動くでしょう。だから、気配がざわざわするんです。誰かが近づいてくると、肩を叩かれたように思ってしまって…。」
「……なるほど、それで妖精か。」
「…悲鳴嶼先輩もそんなことありますか?」
先輩は首を横に振った。
「私は違う。私は盲目で、その分他の機能が発達しているだけだ。霧雨のものはもっと特別なものだろう。」
「と、言いますと…?」
「詳しいことはわからない。だが感じるものは仕方があるまい。気配のざわめきに心を乱されぬようにするしかない。」
そう言われても、今も落ち着かない。
そこかしこで這いずり回るような、生々しい気配がうごめいているのだから。
「受け入れることだ……辛かろうが。」
「受け入れる…。」
「そのざわめきを当たり前だと思うことだ。誰になんと言われようとも。」
私はしばらく考えた。
皆に変な目で見られている気がした。気配に敏感だなんて。だって私、今どこで皆がどんな風に動いてるのかわかるんだもの。それって気持ち悪くないかな。気にしないでおこうって思っても、気になるんだもん。
カナエだって、そう。
「友達に、エスパーって疑われたんです。でもそれはしょうがないこと…なんですか。」
考えて出てきた質問が少し幼稚っぽかった。
少し恥ずかしくて縮こまっていると、悲鳴嶼先輩が答えてくれた。
「そうだ。」
私は思いっきり殴られたような、すさまじいショックを受けた。
「お前に関わる全ての事象が霧雨を作り上げている。」
そんな私をよそに先輩は話し続けた。
「それらを自ら否定するのは、悲しいことだ。」
「……?」
「疑われようとも霧雨という人間は変わらぬ。それとも、お前の友達はそれだけでお前を見放すのか。」
先輩の言っていることは難しくて。
馬鹿な私は完全に理解できなくて。
それでも。
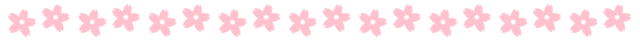
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする