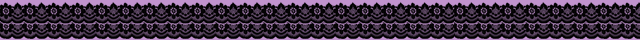
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
オマエはおれ(ら?)のモノ【おそ松さん】
第6章 恋の歯車、回り始めました〈カラ松〉
「・・・っ花子、ほ、本当に良いのか?」
『良いってナニが?』
「だ、だ、だからだな・・・その・・・あ、あれだ!」
『どれよ?』
慌てているカラ松くんが可愛くて思わず笑みが溢れる。
ラブホテルの一室で、お互いにシャワーを済ませて汗と共に酔いも流して。肌触りの良いガウンに袖を通し、キングサイズのベッドに二人で寝転ぶ。
大人の男女がここまで来たら、することは決まっている。なんならここに入った時点で私はカラ松くんに抱かれることを想定していたし、同意している。
それなのに、だ。
カラ松くんときたら、すっかり冷静さを取り戻していて冷や汗をかきながら何度も「本当にいいのか?」を繰り返すばかりで、キスは愚か私に触れてもこないのだ。
「連れ混んでおいてこんなことを言うのもおかしな話なんだが・・・、」
『ん?』
「花子、オマエはもっと自分を大事にした方が良い。」
『へ?』
そんなことをカラ松くんから言われるなんて思ってもみなかった私は、思わず素っ頓狂な声が出てしまった。先程まで合わなかった視線が漸くぶつかり合うと、隣で寝そべる彼はぎごちなく笑っていた。
大事にされていて嬉しいと思う反面、ほんの少しむしゃくしゃとしている気持ちがあって、本音を言ってしまえば何も考えられなくなってしまうほどにぐちゃぐちゃに抱かれたい。
そう思ってしまう理由はよく分からない。
よく分からないけれど、ここまで来て脳裏を過るのは昼間の一松くんばかりで。
・・・これじゃあまるで、。
まるで私が・・・。
「花子、本当は分かってるんじゃないのか?」
『・・・。』
「花子は今も一松のことが、」
好きなんじゃないのか?
そう聞かれてしまったらもう後には引けない気がして、カラ松くんの口を塞ぐように、彼に覆いかぶさりながら食むようなキスを何度も何度も繰り返した。
乾いたリップ音を響かせて、角度を変えながらカラ松くんの熱い舌を自分のソレで執拗に追いかけ回す。やんややんや言っていたくせに、カラ松くんだってさりげなく私の腰に手を回して。
息が苦しくなってどちらからともなく唇をほんの数センチだけ離し、そうして酸素を取り入れた後、再び私たちは抱き合い絡み合いながら貪るようにキスを続けた。
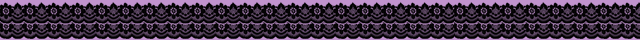
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする