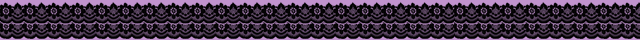
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
オマエはおれ(ら?)のモノ【おそ松さん】
第1章 始まりは突然に・・〈一松〉
『・・・・・、一松くん?』
「あ?なに?」
どれくらいベットの上で抱きしめられていただろうか。しばらくの間、頭を何度も撫でられながら私は一松くんに抱きしめられていた。
ドキンドキンと跳ねる一松くんの心臓の音はこれでもかという程によく聞こえて、耳元にかかる彼の吐息はすごく熱かった。
目の前にいる一松くんは、中学生の頃の一松くんとは違ってすっかりオトコの一松くんになっていた。
そして極めつけは、おへそ辺りに当たる一松くんの硬いアレ。
『・・・あのね、ちょっと言いにくいんだけど、』
「・・・ん?」
『・・そのー、ずっとさっきから当たってるんだよね・・』
「・・・は?」
『・・・これ、』
そっとジャージの上から一松くんのソレに触れると、彼は勢いよくベットから降りて部屋の隅っこへと逃げて行った。
その様はまるで本当の猫のようだった。
「いやいやいやいや、アホなの?なんで触った?クズでゴミのち〇こなんて普通触らないでしょ?」
『ちょ、』
「いやいやいやいや、全然分かんない。あんた怖いんだけど。なんなの、もう。やめて。まじで。」
『いや、』
「てかさー、話の流れよ。おれ童貞のわりに結構頑張って理性保ったわけ。これがグズでゴミの一松だったから良かったものの、おそ松兄さんだったらあんた確実に食われてるからね?その辺ちゃんと理解してんの?」
息付く間もなく珍しくベラベラと喋った一松くんはハァハァと息を整えるとそのまま部屋の隅っこで体育座りをした。
『・・えっと、ごめんね。』
・・あれ?なんで私が謝ってるんだ?
よく分からない状況にひとまず頭を下げる。すごく一松くんが私を大事にしてくれるのは伝わったが、正直私自身そんな価値のある女じゃない。
私は下着姿のまま、一松くんに近づく。一松くんは上目遣いで、ちらっと私を確認するとそのまま目を逸らした。
「・・・服、着なよ。」
『ね、一松くん、』
「・・・なに、」
『・・・シよ?』
「・・・は?」
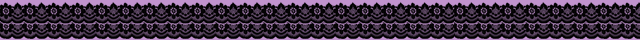
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする