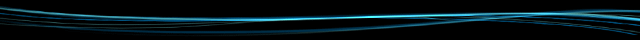
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
ラ・カンパネラ【PSYCHO-PASS】
第2章 成しうる者
――どうか、夢で在りますように。
「「愛している」を振り翳す声に、押し潰されてしまいそうよ。」
「――泉。さっきのアラートは?」
泉が再び病室を訪れれば、慎也が目を覚ましていた。
「エリアストレス上昇だって。智己さんと常守監視官が行ったわ。」
「お前は行かなくて良かったのか?」
「大丈夫だから慎也についててやれって言われちゃったわ。」
そう言いながら、泉は花束を生ける。
「――お前、常守監視官に怒っただろ?」
「やぁね。別に怒ってないわよ。ちょ~っと厭味は言っちゃったけど。」
見透かしている慎也に、泉は苦笑する。
「俺が撃てと言った。彼女に非は無い。」
「分かってる――。分かってるのよ。」
そっと慎也が泉に手を伸ばした瞬間、丁度朱が部屋を訪れる。
「――慎也。私、外に出てるわ。何かいる?」
「悪い。――珈琲、頼む。」
「ん。――常守監視官、ごゆっくり。」
泉は朱の肩を叩けば、耳元で「昼はごめんね」と優しく囁いた。
「――日向監視官。すみませんでした!」
泉が部屋を出れば、朱は勢い良く慎也に頭を下げる。
「執行官に謝る監視官は珍しい。」
「やっぱり怒ってますか?」
「あれがアンタの判断だった。俺が文句を言う筋合いじゃない。」
「私の判断間違ってたんでしょうか?ただチームの足を引っ張って皆を危険に晒しただけだったんでしょうか?」
朱の問いに、慎也はゆっくりと語り始める。
「もう長いこと執行官をやっている。迷うことなく疑うことなく命じられたままに獲物を仕留める猟犬の習性が俺の手には染み付いちまってる。あの銃の言いなりになって何人もの潜在犯を撃って来た。それがこの社会の為になると小奇麗な理屈を鵜呑みにしていつの間にか考えることさえ無くなった。自分がやっている事がなんなのか顧みる事さえ忘れていた。バカな話だ。刑事ってのは誰かを狩り取る仕事じゃなくて誰かを守る仕事だったはずなのにな。」
「――狡噛さん。」
「アンタは何が正しいかを自分で判断した。役目より正義を優先出来た。そう言う上司の下なら俺はただの犬ではなく刑事として働けるかも知れない。」
その言葉に、朱は再び頭を下げた。
「「愛している」を振り翳す声に、押し潰されてしまいそうよ。」
「――泉。さっきのアラートは?」
泉が再び病室を訪れれば、慎也が目を覚ましていた。
「エリアストレス上昇だって。智己さんと常守監視官が行ったわ。」
「お前は行かなくて良かったのか?」
「大丈夫だから慎也についててやれって言われちゃったわ。」
そう言いながら、泉は花束を生ける。
「――お前、常守監視官に怒っただろ?」
「やぁね。別に怒ってないわよ。ちょ~っと厭味は言っちゃったけど。」
見透かしている慎也に、泉は苦笑する。
「俺が撃てと言った。彼女に非は無い。」
「分かってる――。分かってるのよ。」
そっと慎也が泉に手を伸ばした瞬間、丁度朱が部屋を訪れる。
「――慎也。私、外に出てるわ。何かいる?」
「悪い。――珈琲、頼む。」
「ん。――常守監視官、ごゆっくり。」
泉は朱の肩を叩けば、耳元で「昼はごめんね」と優しく囁いた。
「――日向監視官。すみませんでした!」
泉が部屋を出れば、朱は勢い良く慎也に頭を下げる。
「執行官に謝る監視官は珍しい。」
「やっぱり怒ってますか?」
「あれがアンタの判断だった。俺が文句を言う筋合いじゃない。」
「私の判断間違ってたんでしょうか?ただチームの足を引っ張って皆を危険に晒しただけだったんでしょうか?」
朱の問いに、慎也はゆっくりと語り始める。
「もう長いこと執行官をやっている。迷うことなく疑うことなく命じられたままに獲物を仕留める猟犬の習性が俺の手には染み付いちまってる。あの銃の言いなりになって何人もの潜在犯を撃って来た。それがこの社会の為になると小奇麗な理屈を鵜呑みにしていつの間にか考えることさえ無くなった。自分がやっている事がなんなのか顧みる事さえ忘れていた。バカな話だ。刑事ってのは誰かを狩り取る仕事じゃなくて誰かを守る仕事だったはずなのにな。」
「――狡噛さん。」
「アンタは何が正しいかを自分で判断した。役目より正義を優先出来た。そう言う上司の下なら俺はただの犬ではなく刑事として働けるかも知れない。」
その言葉に、朱は再び頭を下げた。
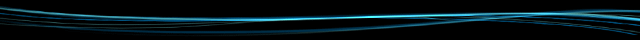
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする