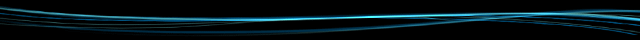
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
ラ・カンパネラ【PSYCHO-PASS】
第22章 鉄の腸
――梔子の匂いが僕を支配する。
「愛しい姫君。君を恋わなかった日が、一日たりともあろうものか。」
「何故だ?君なら理解出来たはずだ。この全能の愉悦を――、世界を統べる快感を!」
「さながら神の如く――、かね?それはそれで良い気分になれるのかも知れないが、生憎審判やレフェリーは趣味じゃないんだ。そんな立場では試合を純粋に楽しめないからね。」
そう言って、槙島は禾生を投げ飛ばす。
「――僕はね。この人生と言うゲームを、心底愛しているんだよ。だからどこまでもプレイヤーとして参加し続けたい。」
「やめ、ろ――。」
「それと一つだけ聞いて置きたい。日向泉を僕の元に送り込んだ黒幕は君かな?」
「――君のお気に召すかと思ったんだ。」
その言葉に、槙島は思い切り禾生の頭を殴る。
「残念ながら、その件で僕を怒らせてくれたよ。あの子はね、もっと尊くあるべきなんだ。下らない事にあの子を巻き込むんじゃない。」
「全能を――、下らないと?」
「あぁ、下らないね。おおかた僕と一緒に泉もシビュラに取り込むつもりだったんだろう?冗談じゃない。彼女は人間であるからこそ美しい。それを歪めるなど冒涜も甚だしいと理解しろ。」
怒りに任せて、槙島が禾生を殴りつける。
「――神の意識を手に入れても、死ぬのは怖いか?」
「ん――、やぁ――!も――、慎也!」
「まだだ。」
静かな部屋に、二人の吐息だけが響く。
その空気を打ち破ったのは、携帯のコール音だった。
「――ッチ、誰だ!」
慎也がそのまま携帯に手を伸ばせば、泉が下で身じろぎする。
『夜分に失礼する。狡噛慎也の番号で間違い無かったかな?』
その声に、慎也は思わず息を呑む。
『今日シビュラシステムの正体を知ったよ。アレは君が命がけで守る程、価値のある物では無い。それだけを伝えておきたくて。では、いずれまた。――泉も元気で。』
一方的に告げられた言葉に、泉は唇を噛み締めた。
「愛しい姫君。君を恋わなかった日が、一日たりともあろうものか。」
「何故だ?君なら理解出来たはずだ。この全能の愉悦を――、世界を統べる快感を!」
「さながら神の如く――、かね?それはそれで良い気分になれるのかも知れないが、生憎審判やレフェリーは趣味じゃないんだ。そんな立場では試合を純粋に楽しめないからね。」
そう言って、槙島は禾生を投げ飛ばす。
「――僕はね。この人生と言うゲームを、心底愛しているんだよ。だからどこまでもプレイヤーとして参加し続けたい。」
「やめ、ろ――。」
「それと一つだけ聞いて置きたい。日向泉を僕の元に送り込んだ黒幕は君かな?」
「――君のお気に召すかと思ったんだ。」
その言葉に、槙島は思い切り禾生の頭を殴る。
「残念ながら、その件で僕を怒らせてくれたよ。あの子はね、もっと尊くあるべきなんだ。下らない事にあの子を巻き込むんじゃない。」
「全能を――、下らないと?」
「あぁ、下らないね。おおかた僕と一緒に泉もシビュラに取り込むつもりだったんだろう?冗談じゃない。彼女は人間であるからこそ美しい。それを歪めるなど冒涜も甚だしいと理解しろ。」
怒りに任せて、槙島が禾生を殴りつける。
「――神の意識を手に入れても、死ぬのは怖いか?」
「ん――、やぁ――!も――、慎也!」
「まだだ。」
静かな部屋に、二人の吐息だけが響く。
その空気を打ち破ったのは、携帯のコール音だった。
「――ッチ、誰だ!」
慎也がそのまま携帯に手を伸ばせば、泉が下で身じろぎする。
『夜分に失礼する。狡噛慎也の番号で間違い無かったかな?』
その声に、慎也は思わず息を呑む。
『今日シビュラシステムの正体を知ったよ。アレは君が命がけで守る程、価値のある物では無い。それだけを伝えておきたくて。では、いずれまた。――泉も元気で。』
一方的に告げられた言葉に、泉は唇を噛み締めた。
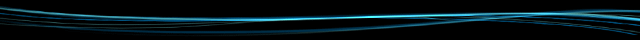
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする